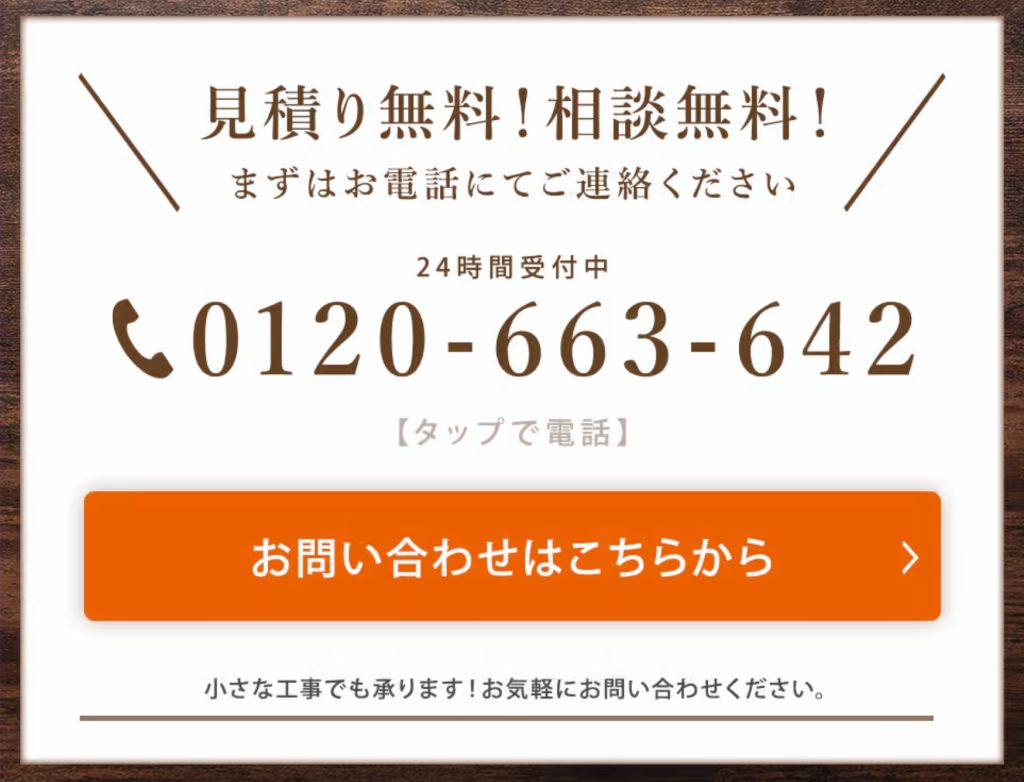屋上の防水工事を検討する際、「工期はどのくらいかかるのか?」と疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。ウレタン防水は工程が多く日数がかかる、シート防水なら短期間で終わるといった情報は多いものの、実際の工期は建物の状況や天候によって左右されるため、正確な目安がつかみにくいのが実情です。
防水工事は建物の寿命を延ばす重要なメンテナンスである反面、生活に影響が出る可能性もあるため、あらかじめ工期を把握しておくことが大切です。
今回は、防水工事にかかる工期の目安や、工期が長引く原因、工法ごとの違いについて詳しく解説します。
さらに、屋上・バルコニーなど施工箇所別の工期や、工事をスムーズに進めるための事前準備のポイントも紹介し、スムーズな工事に役立つ内容をお届けします。
後悔のない防水工事を行うためにも、ぜひ参考にしてみてください。
防水工事の基礎を詳しく知りたい方は、まず 防水工事 の基本解説をご覧ください。
施工内容や費用の目安を知りたい場合は、こちらの 防水工事 の記事が参考になります。
防水工事とは?建物を守るために欠かせない理由
防水工事は、屋上やベランダ、外壁などの外部に面した部位に対し、雨水や湿気が建物内部に侵入しないよう処理する工事です。見た目には分かりにくい施工ですが、建物の安全性・耐久性・資産価値を守るうえで非常に重要な役割を果たします。
特に日本は、梅雨や台風といった雨の多い気候であり、防水性能の低下は雨漏り・内部腐食・空室リスクの増加など、多くの問題を引き起こす可能性があります。
防水工事が必要とされる理由
- 雨漏りや漏水を未然に防ぐ
防水層が劣化すると、建物内部へ水分が浸入し、天井や壁のシミ・カビ・クロス剥がれなどのトラブルが発生します。室内環境の悪化や修繕費用の増加につながるため、予防的な防水対策が重要です。 - 建物の耐久性・資産価値を維持する
水分が構造体へ影響を与えると、鉄筋のサビやコンクリートの爆裂・中性化が進み、建物の耐久性が著しく低下します。さらに、防水状態が良好な物件は、入居者や購入希望者に「管理状態が良い建物」として評価されるため、資産価値の維持にも直結します。
防水工事を怠った場合のリスクとは?
防水工事を長期間行わず、防水層の劣化を放置してしまうと、以下のような深刻な被害に発展する可能性があります。
- 室内への雨漏りや電気設備への影響
- 外壁・屋根内部の腐食や断熱材の劣化
- 入居者からのクレームや早期退去の発生
- 大規模な構造補修が必要になり修繕費が高額化
こうしたリスクを回避するには、10〜15年ごとの防水改修と、定期的な点検・補修が必要です。
このように、防水工事は「見えないから後回し」にされがちですが、建物の寿命と資産を守るために最も基本となる保全工事のひとつです。長く快適に使い続けるために、適切な時期での施工計画を立てることが大切です。
防水工事にかかる工期の目安は?
防水工事は一般的に数日〜1週間程度で完了することが多いものの、建物の種類や施工面積、工事内容によって工期は大きく異なります。このセクションでは、代表的なケースごとに、防水工事にかかる標準的な工期の目安を紹介します。
一般的な防水工事の工期目安(住宅・集合住宅の場合)
ここでは、戸建て・マンション・ビルなど、建物の種類別に防水工事の平均的な所要日数を解説します。事前の見積もりや計画を立てる際の参考としてご活用ください。
| 建物の種類 | 施工面積の例 | 工期の目安 |
|---|---|---|
| 戸建て(ベランダ) | 約10〜15㎡ | 約1〜3日 |
| 戸建て(陸屋根) | 約20〜30㎡ | 約3〜5日 |
| マンション屋上 | 約100〜300㎡ | 約5〜10日(足場含む) |
| ビル屋上(中規模) | 約500㎡以上 | 約10〜14日 |
工期に影響する主な要因
防水工事の所要期間は、単に工法の違いだけでなく、建物の条件や気象状況、現場の準備体制など、さまざまな要因によって前後します。以下は、工期を左右する代表的な要因です。
- 使用する防水工法の種類(塗膜・シート・アスファルトなど)
- 下地の劣化状況や補修の有無
- 施工面積や建物階数
- 天候条件(雨天・低温)
- 足場設置や養生の手間
1. 使用する防水工法の種類(塗膜・シート・アスファルトなど)
防水工法ごとに、施工工程の数や乾燥時間、必要な技術の違いがあります。
特にウレタンやFRPといった塗膜系は、層ごとの乾燥時間が必要であるため、天候の影響を受けやすく、工期が長くなる傾向にあります。一方、シート防水は短期間で施工できることが多く、スピード重視の現場に向いています。
2. 下地の劣化状況と補修の有無
施工面の状態によって、下地補修が必要になるケースが多くあります。
ひび割れ・浮き・旧防水層の損傷などがある場合は、補修工程が追加され、予定より工期が延びる要因になります。
事前に正確な現地調査・診断を行うことが、不要な手戻りの防止につながります。
3. 施工面積や建物の規模(階数・構造)
一般的に、施工面積が広くなるほど工期も長くなるのはもちろん、
高層階やビルの場合は、資材運搬や仮設工事の工程も含まれるため、
戸建てと比べて準備・片付けにかかる時間も多くなります。
また、形状が複雑な建物や段差が多い屋上などは、作業効率にも影響します。
4. 天候条件(雨天・湿度・気温)
防水工事は、気象条件の影響を非常に受けやすい工種です。
特に雨天や高湿度、気温5℃以下の低温環境では、塗膜防水材が正常に硬化せず、施工ができない・仕上がりに不具合が出るリスクがあります。
そのため、梅雨や真冬は工事延期や乾燥待ちによる工期延長が発生しやすいため、施工時期の選定が非常に重要です。
5. 足場設置や養生作業の手間
屋上や外壁などの高所作業を伴う場合、仮設足場の設置と撤去に数日を要するケースがあります。
また、近隣建物や住民への配慮としての養生(飛散防止・遮音・臭気対策)も、
現場環境によっては時間がかかる工程の一つです。
準備工程を軽視すると、後工程に悪影響が出るため、事前段取りがカギとなります。
このように、防水工事の工期は多くの要因が複合的に絡んで決まるため、「どこに施工するか」「どの工法か」だけでなく、「どんな条件か」も合わせて考慮することが大切です。
防水工事にかかる日数や期間について|防水工法ごとの工期比較【用途別】
防水工法にはさまざまな種類があり、それぞれの施工手順や乾燥時間の違いによって工期が変わります。以下の比較表をご覧ください。
主な防水工法と工期の比較
ウレタン塗膜防水、シート防水、アスファルト防水、FRP防水など、主要な防水工法それぞれの特徴と一般的な施工日数を一覧形式で解説します。
用途や予算だけでなく、「どれくらいで終わるか」も選定の重要なポイントです。
| 防水工法 | 特徴 | 工期の目安 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| ウレタン塗膜防水 | 塗布型・複雑形状に対応・乾燥時間が必要 | 約3〜7日 | 屋上、ベランダ、共用部 |
| シート防水(塩ビ等) | 規格品で施工性が高い・天候に強い | 約2〜5日 | 屋上、大型施設 |
| アスファルト防水 | 厚膜・耐久性高い・熱工法やトーチが必要 | 約4〜7日 | マンション屋上、ビル |
| FRP防水 | 硬化が早く小面積向き・強度が高い | 約1〜3日 | バルコニー、陸屋根 |
各工法の施工例(ウレタン防水)
ウレタン塗膜防水は、液状のウレタン樹脂を塗り重ねて防水層を形成する工法で、屋上やバルコニー、共用廊下など、幅広い場所に採用されています。形状に柔軟に対応できるため、複雑な構造にも適応できる点が大きなメリットです。
ただし、塗布後の乾燥・硬化に時間が必要で、天候にも左右されやすいため、工期は比較的長めになる傾向があります。以下は、一般的なウレタン防水の施工工程です。
ウレタン防水の基本的な施工ステップ
- 高圧洗浄・下地清掃
施工面の汚れやホコリを取り除き、密着性を高める準備を行います。 - 下地補修(ひび割れ・段差など)
クラックや段差を補修し、防水層の安定性を確保します。 - プライマー塗布
ウレタン塗料の密着を良くするため、下地に専用プライマーを塗布します。 - ウレタン1層目の塗布 → 乾燥
1層目を均一に塗り、しっかりと乾燥させます(約12~24時間)。 - ウレタン2層目の塗布 → 乾燥
2層目を重ね塗りし、再度しっかり乾燥させて厚みを確保します。 - トップコートの塗布(仕上げ)
紫外線や摩耗から防水層を守るための保護塗装を施します。
このように、複数の工程と乾燥時間が必要になるため、天候の良い期間を確保しながら進めることが重要です。
各工法の施工例(シート防水)
シート防水は、工場で成型された防水シート(塩ビ・ゴムなど)を現場で貼り付けるタイプの防水工法です。品質が安定しており、施工スピードが早いことから、マンション屋上や大型施設で多く採用されています。
乾燥工程が不要で、天候の影響を受けにくいことが大きな利点ですが、下地処理や貼り付け精度が仕上がりに直結するため、丁寧な施工が求められます。
シート防水の基本的な施工ステップ
- 下地の清掃・乾燥確認
施工面の汚れや水分を除去し、密着性を確保します。 - 下地調整・不陸補修
凸凹やひび割れなどを補修し、シートを貼る面を均一に整えます。 - 接着剤または機械固定の準備
塩ビシートの場合は接着剤、ゴムシートでは機械的に固定する工法もあります。 - 防水シートの貼り付け・圧着
継ぎ目にシワができないよう丁寧に貼り、専用のローラーで圧着します。 - 端部・立ち上がり部分の処理
雨仕舞に関わる重要な部分。専用部材やシール材で丁寧に施工。 - シール処理・仕上げ確認
ジョイント部や端部にシール処理を施し、最終確認を行って完了です。
シート防水は、乾燥を待つ必要がなく、面積が大きくても短期間で施工が可能な点が強みです。
一方で、細かな部分には不向きなため、平面の広い屋上などが最適な施工対象となります。
このように工法ごとに工程や工期の考え方が大きく異なるため、建物の用途や形状、求める耐久性に応じて最適な防水工法を選ぶことが重要です。
部位別に見る防水工事の工期と注意点
防水工事は施工する部位ごとに工程や注意点が異なり、同じ工法を使っても場所によって工期が変動します。このパートでは、屋上・ベランダ・外壁・共用部といった代表的な部位ごとに、想定される工期と施工上の注意点を解説します。
屋上の防水工事
屋上防水は施工面積が広く、また足場の設置や養生作業に時間がかかるため、他の部位と比べて工期が長くなる傾向があります。ここでは、屋上防水に特有の工期目安と準備段階の注意点を詳しく解説します。
- 工期の目安:中〜大規模の場合は約5〜10日程度
- 注意点:
- 足場仮設や資材搬入に時間がかかる
- エレベーターや共用部の利用制限が発生する場合あり
- 雨天中断のリスクが高く、スケジュールに余裕を持たせる必要がある
ベランダ・バルコニーの防水工事
ベランダやバルコニーの防水工事は、面積が比較的小さいため短期間で済むことが多いですが、**住居内からの出入りや洗濯物干しの制限など、居住中ならではの課題が伴います。**ここでは、工期の目安に加えて、居住者対応の注意点も取り上げます。
- 工期の目安:1〜3日(FRPやウレタン使用時)
- 注意点:
- 居住中施工の場合は洗濯物や外出動線に配慮が必要
- 下地のクラックが多いと補修工程が追加される
外壁・共用廊下・階段の防水補修
外壁の防水工事では、塗装やシーリングなど他の工事と並行して行われることが多く、全体工期の調整が必要です。ここでは、防水工事が外壁改修の一部として組み込まれる際の工期配分や、他工事との調整ポイントを解説します。
- 工期の目安:1フロアあたり2〜4日程度(状況による)
- 注意点:
- 共用部使用制限により、入居者の協力が必要
- 雨天や気温低下により工程がずれる場合あり
工期短縮のコツと事前準備
共用廊下や階段は、日常的に住民が利用する場所であるため、通行制限や騒音への配慮が求められ、時間帯や作業工程の制約により工期が延びるケースもあります。このセクションでは、共用部における防水工事の工期の考え方と対応の工夫について解説します。
- 早期の業者選定と事前調査で無駄な工程を削減
- 施工面積をまとめて一括対応することで効率化
- 乾燥時間が短い工法(FRPなど)を選ぶことで時短可能
- 梅雨・冬季など天候リスクの高い時期は避けるのが無難
工期が長引く原因とは?
防水工事は比較的短期間で完了する工種と思われがちですが、計画通りに進まないケースも少なくありません。工事が長引くことで、コスト増や入居者・テナントとの関係悪化にもつながるため、「なぜ工期が延びるのか」をあらかじめ理解しておくことが非常に重要です。
1. 天候不良(雨・強風・低温)
防水工事は、特に塗膜系工法(ウレタン・FRPなど)で気温や湿度の影響を大きく受けるため、雨天や極端な気温では作業が中断されることがあります。
塗料の乾燥や硬化には一定の条件が必要なため、施工後に連続した晴天日が必要となるのもポイントです。
- 塗膜防水の場合、降雨・高湿度では施工不可
- 5℃未満の低温では塗料が硬化不良を起こす
- 施工前後に乾燥時間が必要なため、連日の雨天で中断・延期が発生しやすい
2. 下地の劣化や不具合の発覚
工事前の目視調査で確認できなかった劣化や損傷が、実際の施工時に明らかになるケースがあります。下地のひび割れや浮き、旧防水層の破損などが発見されると、補修工程が追加となり、想定よりも日数が延びてしまう要因になります。
- 工事開始後に、ひび割れ・浮き・防水層の剥がれなどが判明することも
- 補修工程が追加されると、当初の工程表が大きくズレる可能性あり
- 点検不足や安易な見積もり提示が後のトラブルに直結
3. 資材の納品遅れ・人員の確保不足
繁忙期(春・秋)などは、防水資材や職人の手配が混雑し、工程に遅れが出るケースがあります。特に特注部材や指定メーカー品を使う場合、発注から納品までに時間を要することがあるため、早期準備が不可欠です。
- 繁忙期(春・秋)には職人の確保が難航し、工程の空白が発生しやすい
- 特注部材や特定メーカー品の納品遅れも影響
- 工期内に間に合わない場合、別途仮設対応などが必要になることも
4. 近隣・入居者からのクレーム対応
集合住宅やテナントビルでは、騒音・臭気・共用部の立ち入り制限などが住民や店舗に与える影響が大きく、苦情や要望により作業の一時中断が発生することもあります。こうした対応は工期に直接影響するため、事前の説明や配慮が重要です。
- 騒音・臭い・通行制限などへのクレーム対応で作業一時中断
- とくに共用部・店舗・医療施設では時間制限や制約が多い
防水工事中の住民・テナント対応について
防水工事は建物の安全性維持に欠かせないものですが、居住者やテナントの生活・営業に一時的に影響を与える側面もあるため、丁寧な対応と説明が非常に重要です。工事の印象が悪ければ、住民からの信頼低下やクレームの増加にもつながりかねません。
どのような影響が出やすいのか
防水工事中は、足場の設置による視界の遮断や、塗料の臭気、通行規制などの影響が発生します。特に屋上やバルコニーの防水では、作業中の立ち入りが禁止される場合が多く、洗濯物や通行ルートへの配慮が求められます。
主な対応策と準備のポイント
住民・テナントとのトラブルを避けるためには、事前の十分な説明と告知が不可欠です。案内文や掲示板での周知だけでなく、工程表の配布や質問受付の窓口を明示しておくと安心感を与えられます。
また、低臭塗料の使用や工事時間の調整、養生の強化など現場ごとの工夫も重要です。
住民の信頼を得るための工夫
住民やテナントに「配慮されている」と感じてもらうことが、工事中のストレスを軽減するカギとなります。そのためには、担当者が顔を出して丁寧に説明したり、進捗状況を定期的に報告することで安心感を高めることが効果的です。
また、工事完了後に「ご協力ありがとうございました」と一言伝える姿勢も、印象の向上につながります。
主な対応策とポイントのまとめ表
| 対応内容 | 解説 |
|---|---|
| 事前説明会・掲示 | 工事期間・時間帯・作業内容を明記した案内の配布/掲示板での周知が基本 |
| 日中の作業調整 | テナント・住民のライフスタイルに配慮した時間帯設定(午前・午後等) |
| 臭気対策 | 換気の指導/低臭タイプの塗料使用検討/養生強化 |
| 苦情窓口の設置 | 現場担当者の連絡先を明記し、迅速対応可能な体制を整備 |
防水工事の工期を短縮するには?
防水工事は施工環境や気象条件によって工期が延びることもありますが、**事前準備と工法選定によって効率化し、工期を短縮することが可能です。**ここでは、工期をできるだけ短く・スムーズに進めるためのポイントを解説します。
工期短縮のための主な工夫
- 事前調査・診断を正確に行う
施工前に下地の状態や劣化状況を十分に確認しておくことで、施工中の追加工事や想定外の手戻りを減らすことができます。 - 施工管理体制の整備
工程表を詳細に作成し、各作業工程の職人や担当者が連携できる体制を整えることで、無駄な中断を回避できます。 - 乾燥時間の短い工法を選ぶ
FRP防水や速乾タイプのウレタン防水など、硬化が早く作業日数を圧縮できる工法を選択することで、全体の工期短縮が可能です。 - 天候リスクの少ない時期に工事を計画する
梅雨や真冬は避け、気候が安定している春・秋に施工することで天候による中断リスクが減り、結果的に短期間で完了しやすくなります。 - 部分的な施工で工期を分散させる
一括での全面工事が難しい場合は、優先度の高い箇所から順に段階的に施工する方法も有効です。
防水工事の工期が短すぎるケースは注意が必要
防水工事は建物を長く守るための重要な工事であり、適正な工程と乾燥時間を確保することが欠かせません。工期が極端に短すぎる場合には、一見スピーディーでメリットがあるように感じられますが、実際には不具合や将来的な修繕リスクを高める原因となります。
ここでは、工期が短すぎる場合に起こりやすい注意点と適切な工事の見極め方を解説します。
工期が短すぎる防水工事の注意点1.乾燥時間や養生を省くと不具合の原因に
防水材には、それぞれ適切な乾燥時間や養生期間が定められています。工期を短くするためにこの工程を省いてしまうと、塗膜の硬化不良や密着不良が起きやすくなり、防水性能が十分に発揮されません。数年以内にひび割れや浮きが発生するリスクが高まります。
工期が短すぎる防水工事の注意点2.工期を優先しすぎると将来の修繕費が増えることも
短い工期を重視して施工不良が起きると、数年後に再度大規模な修繕を行わなければならなくなる可能性があります。結果として、工期を急いだことで初期費用は抑えられても、中長期的には余計なコスト増につながるケースが少なくありません。
防水工事における適正な工期の見極めポイント
- 使用する工法ごとの標準工期を確認する
- 乾燥・養生時間が確保されているかをチェックする
- 極端に短い工期を提示する業者には理由を確認する
防水工事は「短期間で済む業者=優良業者」とは限りません。建物の寿命を延ばすためには、十分な工程を踏んだ適正な工期を重視することが大切です。
よくある質問(FAQ)
防水工事に関して寄せられることの多い質問とその回答を以下にまとめました。工事を検討中の方や管理者の不安や疑問を解消する目的でご活用ください。
Q. 防水工事は雨の日でもできますか?
A. 雨天時は原則として施工できません。特に塗膜防水は乾燥が不十分だと仕上がり不良につながるため、施工日の変更や中断が発生します。
Q. 工事中でも建物は使えますか?
A. ほとんどの場合は居住・営業しながらの工事が可能です。ただし、屋上やバルコニーなど一部の立ち入り制限や通行制限が発生することがあります。
Q. 工事中の騒音や臭いが心配です。対策はありますか?
A. 防音・低臭対策は可能です。事前に防音養生や低臭タイプの塗料を指定することで、住民や近隣への配慮を強化できます。
Q. 工期を短くする方法はありますか?
A. 速乾型の工法を採用したり、施工面積を絞って分割実施することで短縮可能です。ただし品質とのバランスを考慮することが重要です。
Q. 工事費用は日数によって変わりますか?
A. 一般的には工法と面積で決まるため、日数が直接の費用変動要因になることは少ないですが、長期化による人件費や仮設費が加算されることもあります。
防水工事の工期を把握して工事を成功に導く|まとめ
防水工事は、建物の寿命や資産価値を守る上で欠かせない重要なメンテナンス工事です。
工期については、建物の種類・工法・施工箇所・天候条件などによって変動しますが、一般的には戸建てで1〜3日、マンションやビルでは5〜10日程度が目安です。
工法ごとの特徴や下地状態の把握、そして住民・テナントへの配慮を含めた計画的な進行により、無駄のない工事とトラブル防止が実現できます。
特にウレタンやFRP、シート防水などの工法ごとの工期や向き・不向きを理解して選定することが、スムーズな進行のポイントとなります。
天候や管理体制によっては工期が延びるリスクもありますが、事前の段取りと適切な情報共有で大きく回避することが可能です。
防水工事を計画する際は、「いつ、どこを、どの工法で、どのくらいの時間をかけて行うか」を明確にし、信頼できる業者と相談しながら進めることをおすすめします。
防水工事・修繕工事は新東亜工業がおすすめ!

中間マージン0だから他社より安い費用で工事が可能
※中間マージン=仲介手数料
- 大規模修繕工事
- 解体工事
- 防水工事
- 外壁塗装
- 屋根工事
- シーリング工事
- 長尺シート工事
- 下地補修工事
- 足場工事
- タイル工事
- 洗浄工事
- 電気、水道、外溝工事等
大きな強みは「自社で完結」
施工価格と見積りには絶対的な自信を持っていますので、他社との相見積りも大歓迎です。
ご予算と現場調査の結果、長期的な視点での資産価値向上をバランスよく考慮し、お客様にとってベストな選択肢をご提案します。