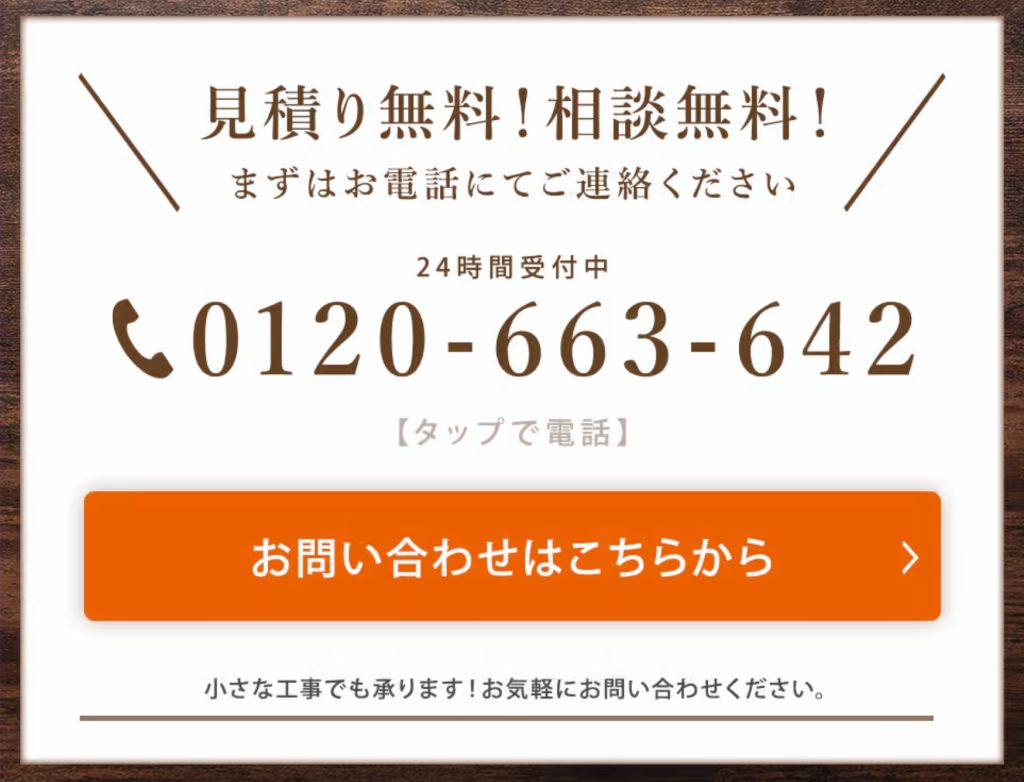雨樋(あまどい)は、屋根に降った雨水を効率よく集めて排水口まで導き、建物を水による劣化から守るために欠かせない設備です。外壁や基礎部分に雨水が直接当たるのを防ぎ、住宅の寿命や快適性を保つうえで重要な役割を果たしています。
しかし、雨樋は普段あまり注目されることがなく、破損や詰まりに気づかないまま放置してしまうケースも少なくありません。適切な素材選びや定期的なメンテナンス、そして早めの修理対応が、建物全体の保護につながります。
本記事では、雨樋の基本的な役割や構造、代表的な種類と素材の違い、劣化によるトラブル例、掃除・修理の方法、さらには費用の目安までを、初めての方にもわかりやすく解説します。雨樋の点検や交換を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
建築確認申請は、私たちの生活空間を形作る建物が安全でありながら、快適かつ法的な基準に適合していることを保証するためのものです。
新しい家を建てる夢・築年数のたったマンションを改修する計画・ビジネスのための商業施設を構築する際には、この手続きが必ず必要になります。
しかし、多くの人にとって建築確認申請は複雑で手間がかかるものと捉えらていますが、しっかり内容を把握しておけばスムーズに進められます。
そこで本記事では、建築確認申請の基本からその目的や必要性や基準など、わかりやすく解説していきます。
多くの方が住むマンションの安全を維持しながら入居者が安心して暮らし続けられるように「よくわからなくて不安だ」という方は、建築確認申請について学んでいきましょう。
建築確認申請とは
建築確認申請は、建築基準法に適合した建物を建築する際に必要な重要な手続きです。
この手続きを通じて、安全性や品質の確保が図られます。
建築確認申請
建築確認申請は、建築基準法に適合した建築物を建設するために、都道府県や市区町村の建築主事に対して提出する申請書類です。
この申請書類には、建築計画概要書や図面などが含まれ、建物が基準法に準拠していることを証明します。
審査と確認済証の発行
申請書類が提出されると、都道府県や市区町村の建築主事が審査を行います。
審査の結果、建築物が基準法に適合していることが確認されれば、確認済証が発行されます。
この確認済証は、工事を始める際に必要不可欠な書類です。
変更や届け出の必要性
建築確認申請が完了したからといって、すべてが終わるわけではありません。
工事内容の変更や工期の延長が必要な場合は、変更届や延長届を提出する必要があります。
建築確認申請は、建物の安全性と品質を確保するために重要であり、その過程での正確な届け出が求められます。
リフォームで建築確認申請をする目的
リフォームで建築確認申請を行う主な目的は、以下のような点が挙げられます。
法令遵守の確保
リフォーム工事によって建物の構造や間取りが変更される場合、地方自治体の建築基準法に則って適切な基準を満たしていることを確認する必要があります。
建築確認申請を行うことで、法令遵守の義務を果たし、安全かつ適切なリフォームを行うことができます。
建築物の安全性の確保
リフォーム工事によって建物の構造が変更される場合、耐震性や耐火性などの安全性が損なわれる可能性があります。
建築確認申請を通じて、建物の安全性を確保するための必要な対策や補強が適切に行われることが期待されます。
保険やローンの利用
建築確認申請が行われたリフォーム工事は、一定の基準を満たしているため、保険やローンの利用がしやすくなります。
金融機関や保険会社は、建築確認申請が行われたリフォームに対して、より信頼性を持って取引を行う傾向があります。
将来の売却や賃貸に対する影響
建築確認申請が行われたリフォーム工事は、将来の売却や賃貸においても査定や評価が高まる可能性があります。
建築確認申請によって、工事内容や建物の状態が正確に記録され、信頼性のある情報として活用されることが期待されます。
マンションのリフォームにおける建築確認申請の対象
マンションのリフォームにおける建築確認申請の必要性は、工事の規模や内容によって変わります。
リフォームの際に建築確認申請が必要かどうかを判断する際には、以下のポイントに留意することが重要です。
リフォームの規模と建築確認申請
大規模なリフォーム
建物の大規模修繕工事に関わるような変更・増築・用途変更などの場合には、建築確認申請が必要です。
主要構造部分の修繕や模様替えも該当します。
小規模なリフォーム
木造2階建て以下の住宅で、増築を伴わない限り建築確認申請は不要です。
屋根の葺き替えや外壁の改修などの軽微なリフォームは、確認申請の対象外となります。
確認申請の対象と例外
対象
大規模なリフォームには必ず確認申請が必要です。
これには、増改築や大規模な構造部分の修繕が含まれます。
特に、準防火地域内での増築や増改築は、面積にかかわらず確認申請が必要です。
例外
木造2階建て以下の住宅や特定の建物において、一部の小規模なリフォームは確認申請の対象外となります。
ただし、これらの例外にも増改築や構造変更が含まれる場合、確認申請が必要です。
リフォーム計画を立てる際には、建築確認申請の有無や手続きについても十分に調査し、適切な対応を行うことが重要です。
建築確認申請の判断基準
建築確認申請は、建築物の計画や構造が法令に適合していることを確認する重要な手続きです。
申請の際には、特定の基準に従って審査が行われます。それらの判断基準について解説します。
建築基準法の適合性
建築確認申請が受理されるためには、建築基準法に則った建物であることが必要です。
これは、耐震性、耐火性、建物の構造など、法律で定められた基準を満たしているかどうかを意味します。
建物の用途と規模
建築確認申請の判断基準には、建物の用途と規模も含まれます。
住宅、商業施設、工場など、それぞれの用途に応じた基準があります。また、建物の規模や階数も、申請の審査に影響を与えます。
安全性と公共性
建築確認申請は、建物の安全性と公共の利益を考慮して審査されます。
建物が周囲の環境や安全基準に適合し、周辺住民や利用者に対するリスクを最小限に抑える必要があります。
環境への配慮
近年では、環境への配慮も建築確認申請の重要な要素となっています。
省エネルギー、再生可能エネルギーの利用、廃棄物の処理など、建物が持続可能な形で環境に配慮しているかどうかが判断されます。
地域の都市計画
地域の都市計画や建築制限区域に応じて、建物の外観や高さなどが規定されています。
建築確認申請では、これらの地域規制に準拠しているかどうかも重要な判断基準です。
雨樋(あまどい)は建物にとって欠かせない存在であり、屋根に降った雨水を効率よく排水し、外壁や基礎部分の劣化を防ぐ役割を担っています。普段あまり意識されることは少ないものの、住宅の寿命や快適性に大きく関わる重要な設備です。この記事では、雨樋の基本構造や種類、よくある劣化トラブル、掃除・修理方法、費用相場などをわかりやすく解説します。
雨樋とは?基本の役割と構造を解説
雨樋は、屋根に降った雨水を集めて排水設備や地面に導くための排水設備です。雨水がそのまま屋根から落ちると、建物の外壁を汚したり、基礎の部分を濡らしてしまい、劣化の原因になります。さらに、水たまりや跳ね返りによって地面がえぐれるなど、住宅の安全性や美観にも悪影響を及ぼします。
雨樋は主に以下の部材から構成されています。
- 軒樋(のきどい):屋根の下端に設置され、流れてくる雨水を受け止めます。
- 竪樋(たてどい):軒樋で受けた水を下へ流す縦方向の樋です。
- 集水器:軒樋と竪樋の接続部分で、水を効率的に集めます。
- エルボや継手:配管の方向転換や接続に使用されます。
これらが組み合わさることで、屋根全体の排水システムが完成します。
雨樋の種類とそれぞれの特徴
雨樋は材質や形状によっていくつかの種類に分かれており、建物のデザインや耐久性、費用などに応じて選ぶことができます。
材質別の種類
- 塩ビ(プラスチック)製は、安価で加工しやすく、最も広く使用されている素材です。ただし、紫外線や寒暖差に弱く、長期間使用すると割れやすくなります。
- ガルバリウム鋼板は、金属製ながらサビに強く、軽量で耐久性にも優れており、近年多くの住宅で採用されています。
- 銅製は、高級住宅でよく使われる素材で、時間が経つと味のある色合いに変化し、美観を楽しめます。ただし非常に高価です。
- ステンレス製は、サビに強く頑丈なため、工場や大型施設などで多く採用されます。
形状別の種類
- 丸型は、水の流れがスムーズで詰まりにくく、安定した排水性能があります。
- 角型は、シャープでモダンな印象を与えるため、近代的な建物に人気があります。排水能力が高いのも特徴です。
「とゆ」と「とい」とは|雨樋の名称について
雨樋の漢字表記は「雨樋(あまどい)」ですが、実際の会話や資料では「とい」「とゆ」など、異なる読み方が使われることがあります。「とい」は主に関東地方を中心に使われる呼称で、「とゆ」は関西地方などで多く使用されています。どちらも同じく雨樋を指す言葉で、意味や役割に違いはありません。
また、建築現場では「軒樋(のきどい)」や「竪樋(たてどい)」という専門用語も用いられます。軒先を伝う雨水を受け止めるのが軒樋で、そこから地面方向へ導くのが竪樋です。これらの正しい呼び方や仕組みを理解しておくことで、修理や業者とのやり取りもスムーズに行えるようになります。
雨樋のよくある劣化・トラブルとその原因
雨樋は長年使用することで劣化や破損が生じやすくなります。主なトラブルは以下のようなものがあります。
詰まりは、雨樋に落ち葉やゴミ、鳥の巣などが溜まることで発生します。詰まると雨水が流れずにあふれ、外壁に流れ出たり、水が滞留して雨樋が重くなり破損する原因になります。
破損・割れは、紫外線による経年劣化や、積雪、台風などの自然災害で起こります。樋自体にひび割れがあると雨水が漏れ出し、周辺の壁材を劣化させてしまう恐れがあります。
歪み・外れは、支持金具が劣化したり、強風で樋が揺れたりして徐々に傾きが悪くなることで発生します。傾斜が正しく保たれないと排水能力が大きく落ちます。
雨樋の修理・交換が必要なサインと時期
雨樋が正常に機能していないと、以下のような症状が現れます。
- 雨の日に「ポタポタ」という異音がする
- 軒下から雨水が垂れ流れている
- 外壁に雨だれの跡がついている
- 雨樋が目に見えて傾いている
こうした症状がある場合、修理または交換の検討が必要です。雨樋の耐用年数はおよそ15〜20年ですが、使用環境によっては10年程度で劣化することもあります。定期的に点検しておくことで、大きなトラブルを防ぐことができます。
雨樋の掃除・メンテナンス方法
雨樋のトラブルは、定期的な清掃と点検でかなりの割合を防ぐことができます。1階部分であれば、以下の手順で自分でも掃除可能です。
まず、手袋をして落ち葉やゴミを取り除きます。次にホースなどで水を流して、排水の流れを確認しましょう。もし水がうまく流れない場合は、詰まりがある可能性があるため、高圧洗浄機の使用や専門業者への依頼も検討してください。
ただし、2階以上の高所作業は転落のリスクがあるため、自力で行うのは危険です。無理せずプロに任せることが安全かつ確実です。掃除の目安は年に1〜2回。特に秋は落ち葉が溜まりやすいため、重点的な点検をおすすめします。
雨樋修理・交換の費用相場
雨樋工事の費用は、使用する部材、施工範囲、足場の有無などによって変動します。
| 工事内容 | 単価の目安(税抜) |
|---|---|
| 部分交換(1m) | 2,000〜5,000円程度 |
| 全交換(戸建て) | 15万〜40万円程度 |
| 足場設置 | 10万〜20万円程度 |
建物の規模が大きくなるほど、足場費用や人件費がかさみます。信頼できる複数業者から見積もりを取り、適正価格での施工を目指しましょう。
大規模修繕工事の新東亜工業はお客様満足度98%

お客様満足度98% ★★★★☆
新東亜工業が選ばれる理由
- 仲介業者を介さない工事で余分な外注費をカットできる
- 確かな品質と施工スピードが強み
- お客様満足度脅威の98%
- 個人宅以外にマンションなどの大規模修繕にも対応
\\中間マージン0だから他社より安い//

雨樋トラブルを防ぐためにできること
日頃から雨樋の状態を観察することが、トラブルの早期発見につながります。特に以下の予防策がおすすめです。
- 年1〜2回の定期点検を習慣化する
- 雨樋ネットや落ち葉防止カバーを設置し、詰まりを防止
- 屋根や外壁のリフォーム時に雨樋も一緒に交換して、足場費用を効率的に活用
小さな不具合も放置すると建物全体に影響を及ぼす可能性があるため、早めの対策が大切です。
信頼できる雨樋業者の選び方
雨樋の修理や交換を依頼する際は、業者選びも重要です。以下のポイントを確認しましょう。
- 現地調査をしっかり行い、症状と対策を丁寧に説明してくれる
- 見積もり内容が明確で、追加料金の発生リスクが低い
- 自社施工であり、保証制度が充実している
- 口コミ評価や施工事例が公開されている
とくに地元密着型の業者は、迅速な対応やアフターケアで高評価を得ているケースが多いため、選択肢に入れてみましょう。
まとめ|雨樋は建物を守る大切な設備。正しい知識と対策を
雨樋は、建物を雨水から守るために設けられている、重要なパーツです。普段は目立たない存在ですが、劣化やトラブルが起きるとその重要性を実感することになります。適切なメンテナンスと早期対応を心がけることで、大切な住まいの寿命を伸ばすことができます。今一度、雨樋の状態を確認してみてはいかがでしょうか。
防水工事・修繕工事は新東亜工業がおすすめ!

中間マージン0だから他社より安い費用で工事が可能
※中間マージン=仲介手数料
- 大規模修繕工事
- 解体工事
- 防水工事
- 外壁塗装
- 屋根工事
- シーリング工事
- 長尺シート工事
- 下地補修工事
- 足場工事
- タイル工事
- 洗浄工事
- 電気、水道、外溝工事等
大きな強みは「自社で完結」
施工価格と見積りには絶対的な自信を持っていますので、他社との相見積りも大歓迎です。
ご予算と現場調査の結果、長期的な視点での資産価値向上をバランスよく考慮し、お客様にとってベストな選択肢をご提案します。
多くの人が居住して生活を送るマンションは、さまざまな資材を用いることによって形作られています。
なかでも、マンションの鉄部はさまざまな場所で見受けられ、日常的に使用されています。
鉄部にあたる部分は、駐輪場・玄関の扉や枠・手すり・防火扉・給水管などが挙げられます。
長きにわたって良い状態で鉄部を使用していくためには、鉄部の塗装工事が必要です。
鉄部における塗装工事は頻繁に行うものではありませんが、定期的なメンテナンスを必要とし、適切な処置を行わなければさまざまなリスクに見舞われます。
そこで今回は、マンションの鉄部塗装工事における適切な周期をはじめ、工事の必要性や工事の流れなどの詳細についてご説明いたします。
鉄部とは?なぜ鉄部塗装工事が必要なの?
マンションにおける鉄部と聞いて、どのような箇所を思い浮かべますか。
基礎に使用されている鉄筋は鉄で作られていますが、鉄部には含まれません。
鉄部と言われる箇所は、下記のものが挙げられます。
- エレベーターに使用されている扉や枠
- 鉄や鋼で作られていた外階段
- 玄関に使用されている扉や枠
- 非常階段の扉
- 鉄製の駐輪場や駐車場
- 鉄や鋼製の手すり
- 防火扉
- 電気・水道・ガスなどの設備を収納したメーターボックス
- 消火栓設備を収納した消火栓ボックス
- 各家庭に飲料水を供給する役割を持つ給水管
- 屋上や屋根に設置された避雷針
名称のとおり、鉄部は鉄または鋼で作られているものを指します。
ほとんどのものが室内ではなく屋外に設置されており、風や雨などの影響を受けやすい点が特徴です。
マンションの新築当初は、鉄部に塗装が施されているため、見た目や機能において問題がありません。
しかし、風や雨などの影響を長年にわたって受け続けると鉄や鋼は色あせ・汚れ・塗膜の浮きや剥がれ・ひび割れなどを引き起こします。
さらに劣化した部分に雨水が浸入すると、さびで劣化します。
鉄部のさびは機能や耐久性に問題が生じるさせるだけでなく、美観にも影響するでしょう。
機能性や美観が損なわれてしまうとマンションの資産価値は下がり、入居を希望される方が減る原因になる可能性があります。
そのため、マンションを良い状態で保ち続けるためには、鉄部の塗装を定期的に行うことが大切です。
鉄部の劣化を放置するリスク
マンションにおいて、外階段の色あせや玄関扉の塗膜浮きなどが起こっていませんか。
そのような症状が見られる場合は、塗装工事を検討しましょう。
もし鉄部の劣化を放置してしまうと、下記のようなリスクが想定されます。
さびによる機能性の低下
「鉄製の扉がさびによって開きにくくなった」「開閉するたびに扉から異音がする」という経験はありませんか。
鉄部は雨や空気によってさび発生し、機能性を低下させます。
火事の際に消火栓ボックスがなかなか開かないという事態が引き起こしてしまうと、居住者の生命にも関わる可能性も考えられるでしょう。
各箇所における機能をしっかりと果たすためには、定期的な塗装工事が必要です。
美観が損なわれる
新築当初は鉄部への塗装工事が行われているため、見た目がきれいです。
しかし、時がたつほどに劣化は進みます。
定期的な塗装工事を行わない場合、色あせが進んで見た目が悪くなるでしょう。
手入れされていない建物は居住者や居住希望者へ悪い印象を与えてしまい、資産価値が下がる原因です。
多くの方に居心地の良さで選ばれる快適な場所を維持するには、定期的な塗装工事が欠かせません。
鉄部の耐久性が損なわれる
色あせや塗膜浮きを放置していると、鉄部の耐久性は損なわれてしまいます。
鉄部は風や雨の影響を受けやすく、サビが発生した部分は対応しなければ、より範囲を広げ内部まで進行します。
振動や接触によってボロボロと鉄部の一部がとれたりする状態になると、鉄部は安全な状態とはいえません。
見た目だけではなく、耐久性の問題で居住者へ不安を与えてしまうでしょう。
また、鉄部の取り換えや補修には、多くの時間や費用が掛かります。
コストを抑えながら安全に使用し続けられる環境を整備するためには、鉄部のメンテナンスが重要です。
鉄部が劣化する症状
マンションの鉄部が劣化する症状として、どのようなものが見られるかご存じでしょうか。
塗装工事を検討する際には、建物の劣化状況を踏まえておくことが必要です。
劣化の症状は、段階的に起こります。
以下のような劣化の症状がみられる場合は、注意しましょう。
艶がなくなる・色があせる
鉄部が劣化することによってまず艶がなくなり、色あせが生じます。
劣化によって塗膜表面に目に見えないほどの凹凸が生じ、光の反射が均一にならないことが原因です。
艶落ちや色あせなどの症状が現れる目安としては、前回の塗装工事から約3年と言われています。
チョーキング現象の発生
鉄部に触れてみて手に塗料の色がついた場合、チョーキングが起こっています。
チョーキング現象とは塗料に含まれる樹脂が太陽の光・熱・雨水によって劣化し、塗料のなかにある顔料が表面に出てしまう症状です。
症状が現れる目安としては、前回の塗装工事から約3〜5年といわれています。
ひび割れ・剥がれ
鉄部の劣化が進むと、ひび割れや剥がれが生じます。
ひび割れや剥がれは耐久性を損ねてしまうため、注意が必要です。
前回の塗装工事より、7年前後が症状の現れる目安とされています。
鉄部塗装工事の周期目安
マンションの鉄部を良い状態で保つには、鉄部の塗装工事が欠かせません。
しかし、どのような周期で行うのかについて、悩まれる方も多くいらっしゃいます。
一般的な周期の目安としては、前回の工事から約3〜6年が目安です。
前回の工事から年数が経って劣化の症状が見られる場合は、鉄部の塗装工事について検討してみましょう。
また、前回の工事から年数が経過していなくても、著しい劣化の症状が見られる場合は、施工を行う会社への相談が賢明です。
日々における劣化の状況を見極めるためには、定期的な点検を怠らないように行いましょう。
定期的な点検を行うことで劣化の状況をいち早く把握し、早急に対応できます。
鉄部塗装工事の流れ
マンション鉄部の塗装工事は、どのような流れで行われるのでしょうか。
施工を依頼する前に、進め方について知っておくことが大切です。
鉄部における塗装工事は、下記のような流れで行われます。
- STEP
ケレン
サンドペーパーや専用の電気工具を使い、鉄部に付着している古い塗膜やさびを落とす作業がケレンです。
ケレンによる下処理を行った後は、鉄部の表面を傷つける目粗しをして塗料を密着させやすい状態をつくります。
- STEP
養生
塗装箇所以外は塗装の必要がないため、周囲を養生します。
マスキングテープやビニールテープを使い、塗料の飛散や塗り間違いを防ぎます。
- STEP
下塗り
下塗りでは、さび止めの塗料を塗ります。
油性タイプ・エポキシ樹脂タイプ・ウレタン樹脂タイプなどの種類があり、さびの状況に応じたものを使用します。
- STEP
中塗り・上塗り
下塗りが乾燥したら、中塗りと上塗りです。
中塗りは下塗りしたさび止め塗料を保護する効果があり、重要な工程です。
乾燥した中塗りの上に上塗りを行い、乾燥したら完了です。
住民が気をつけるポイントとは
鉄部の塗装工事は、居住者から了承や協力を得なければ、進めていくことが難かしい場合もあります。
居住者の理解を得るためには、下記のポイントを押さえておきましょう。
十分な換気
鉄部における塗装工事では、さまざまな塗料を使用します。
塗料にはにおいがあり、換気が必要です。
玄関の扉を塗装する際は、室内の換気をしっかりと行いましょう。
また、外階段や消火栓ボックスなどの共有部分で塗装が行われる際は、工事の時間帯や施行場所について把握しておくことが重要です。
塗ったばかりの部分に触らない
塗料を塗ったばかりの部分は、塗料が乾いておらず取れやすいです。
手についてしまうと、なかなか取れない場合がありえます。
また、歩いている際にバッグや服についてしまうことも考えられるため、できるだけ触れないように注意を促しましょう。
車両における養生を依頼する
駐輪場や駐車場での塗装工事は、養生を行わないと自転車・バイク・自動車などを汚してしまいます。
塗料は取れにくいため、大切な車両を守るためにも養生が必要です。
養生には養生シートやビニールなどが使われており、取り外すには時間がかかります。
そのため、外出時には養生を外す時間も含め、余裕を持った行動が必要です。
在宅待機
玄関の扉を塗装する場合、在宅待機が必要なことがあります。
その際は、事前に在宅についてのアンケートが取られることがほとんどです。
指定した時間に作業員が訪問しますので、塗装作業が終わるまでは家で待機しましょう。
もし指定の時間帯で外出してしまうと、工事のスケジュールにズレが生じてしまい、スムーズに施工できない場合があります。
また玄関扉の塗装では、周辺の私物が汚れないように移動が必要になることも考慮しましょう。
まとめ
- マンションの鉄部は、外部階段・扉・手すりなどに使われ、風雨などの影響を受けやすい。
- 劣化すると見た目や機能に問題が生じ、さびによる機能低下や美観の損傷、耐久性の低下が起こる可能性がある。
- 鉄部の劣化の症状には、艶落ち・色あせ・チョーキング現象・ひび割れや剥がれなどがあり、定期的な点検が必要である。
- 一般的な塗装工事の周期は前回の工事から約3〜6年であり、劣化の症状や建物の状況に応じて検討されるべきである。
- 塗装工事の流れは古い塗膜やさびを落とすケレン・塗装箇所以外を保護する養生・下塗り・中塗り・上塗りの順で行われる。
- 塗装工事の施行中は、換気・塗料の触れ方・車両の養生・施行中の在宅待機など、住民へのお願いと協力を呼びかけ、工事の円滑な進行と安全を確保する必要がある。
マンションでの生活において、鉄部は日常の生活に欠かせない部位であり、機能性を保つことが大切です。
定期的なメンテナンスをしっかり行い、安全で快適な環境を整備しましょう。