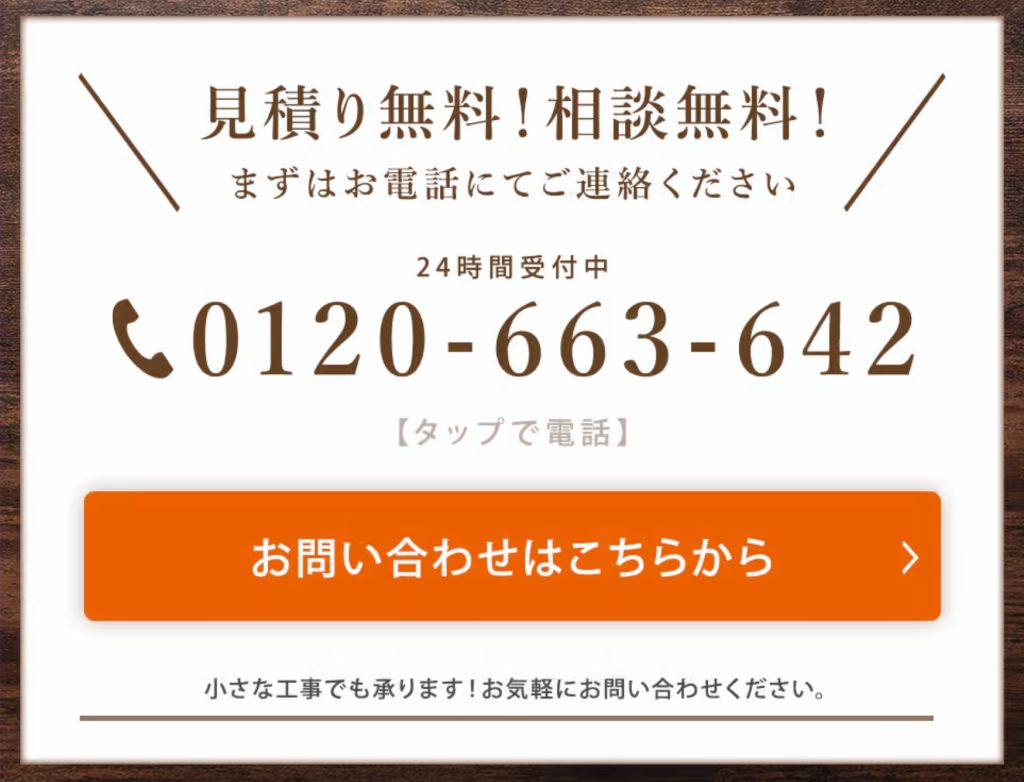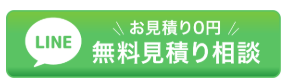大規模修繕は高額な費用がかかるため、確実な施工が求められる重要な工事です。
そのため、万が一の不具合に備えた保証制度の活用が不可欠といえます。
しかし「大規模修繕を終えたけど、これっていつまで保証されるの?」「もし欠陥があったら、どこに連絡すればいい?」そのような悩みを抱えている方は少なくありません。
今回の記事では、大規模修繕における保証の基本知識から、瑕疵保険や完成保証制度についてわかりやすく解説します。
さらに大規模修繕における保証トラブルの事例も紹介しますので、契約を検討している方は最後までご覧ください。
正しい情報を得ることで、施工後に不具合があっても迅速に対応でき、管理組合としても安心して住める環境を提供できます。
大規模修繕について解説
大規模修繕とは、マンションやアパートなどの集合住宅において、経年劣化による不具合や老朽化をまとめて補修・改修する工事のことを指します。外壁塗装、屋上やバルコニーの防水、給排水管の更新、共用部の設備交換など、建物全体の安全性・機能性を長期的に保つために必要な工事が行われます。
通常、築後12〜15年を目安に最初の修繕が実施され、その後も周期的に行われるのが一般的です。資産価値を維持し、住み心地を保つうえで欠かせない取り組みであり、長期修繕計画や住民の合意形成も大切な要素となります。
大規模修繕における保証のしくみとは?
大規模修繕工事における「保証」とは、施工業者が提供するサービスや仕上がりに対して、一定期間内に問題が生じた際に責任を持って修繕・対応することを約束する制度です。工事の完成時に問題が見つからなくても、時間が経ってから発生する不具合や施工不良も対象となるため、非常に重要な概念です。特にマンションのように多くの人が共同で生活する建物では、ひとたび不具合が発生すれば多数の住民に影響が及びます。
保証制度が適切に整備されていない場合、トラブル時に責任の所在が曖昧になり、住民や管理組合が余計な費用や手間を負担せざるを得なくなるリスクがあります。そのため、保証内容は契約前に明文化し、業者選定の重要な評価基準として活用すべきです。
また、保証があることで施工会社側も品質管理を徹底する意識が高まり、工事全体の精度が向上する効果も期待できます。
大規模修繕工事の保証期間の目安
保証期間は工事内容や部位、施工方法などによって異なりますが、以下のような基準が一般的です。
- 防水工事:10年程度(屋上、バルコニー、防水層)
- 外壁補修:5〜10年(クラック補修、タイル貼り替えなど)
- 塗装工事:5〜7年(外壁塗装・鉄部塗装)
- 設備工事:2〜5年(給排水管、電気設備など)
以下にわかりやすく保証内容をまとめました。
| 工事項目 | 一般的な保証期間 | 主な対象部位・内容 | 備考例 |
|---|---|---|---|
| 防水工事 | 約10年 | 屋上、バルコニー、防水層 | 材質により差異(ウレタン・シート等) |
| 外壁補修 | 5〜10年 | クラック補修、タイル貼り替え | 施工範囲や素材により異なる |
| 塗装工事 | 5〜7年 | 外壁塗装、鉄部塗装 | 環境条件(日射・風雨)で劣化速度変動 |
| 設備工事 | 2〜5年 | 給排水管、電気設備、機械室内装等 | 経年劣化や利用頻度により変動あり |
保証期間が長ければ安心というわけではなく、保証の「対象範囲」と「免責事項」も含めて確認することが大切です。たとえば、同じ防水工事でも材料がウレタンかシートかによって耐用年数が異なりますし、施工条件や環境によっても差が出ます。
契約書には必ず保証条項を盛り込み、できれば保証書という形で別途文書化することが望ましいです。施工会社によっては「瑕疵期間」として国が定めた期間以上の独自保証を提供している場合もありますので、他社との比較にも役立ちます。
瑕疵保険とは?
瑕疵保険(かしほけん)は、施工後に見つかった「重大な欠陥」に対して、施工業者が倒産などで責任を果たせない場合に、保険会社が修繕費用を補償してくれる制度です。第三者機関の検査を通じて、施工品質を事前にチェックし、万が一の際に備える制度でもあります。
主な特徴は以下の通りです。
- 国土交通省が認可した第三者機関が検査を行うことで、工事の品質が担保される
- 施工業者が経営困難に陥った場合でも、保険会社が補修対応を行う
- 保険の対象は、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分に限定される
通常、保険期間は10年間となっており、特に防水や構造部における瑕疵(欠陥)が中心です。マンションのように複数人の財産が関係する建物では、非常に有効な制度といえるでしょう。
完成保証制度とは?
完成保証制度は、契約した修繕工事が施工会社の都合(倒産、資金不足など)により途中で停止してしまった場合に備えて、新たな業者の手配や工事費用の一部保証を行う制度です。特に数ヶ月〜1年をかけて行う大規模修繕では、予期せぬ事態への備えとして有効です。
この制度の活用によって得られる主なメリットは以下の通りです。
- 工事中の施工会社の倒産リスクを回避できる
- 工事が途中で止まってしまっても、別業者により再開・完了される
- 一定の費用を保証会社が負担するため、住民の負担を抑えられる
ただし、この制度が適用されるには条件があります。元請施工業者が特定の保証団体や保険会社に登録・加入している必要があるため、施工会社選定時にはその制度の有無も重要なチェックポイントです。
施工会社選びでチェックすべきポイント|保証制度を重視しよう!
保証制度は内容や対応範囲によって大きく異なります。施工後のトラブルを防ぐためにも、契約前に確認すべき重要なチェックポイントを押さえておきましょう。
大規模修繕会社選びのポイント1.保証内容と期間の明示
保証制度を比較する際に最も重視すべきなのが、「何をどこまで保証してくれるのか」です。保証書には対象部位・内容・期間が明記されている必要があります。たとえば、塗装の剥がれや防水層のひび割れなど、具体的な事象に対して何年以内であれば無償対応が可能かを明確に確認しましょう。
また、保証の対象外となる条件(自然災害、使用者の過失など)も合わせて確認しておくことが重要です。
大規模修繕会社選びのポイント2.第三者保証制度の活用
施工会社が提供する保証だけでなく、第三者機関による保証制度にも注目しましょう。たとえば、瑕疵保険や完成保証制度など、公的・中立的な保証制度が用意されていれば、万が一の業者倒産時にも安心です。
これらの制度は管理組合の追加負担で加入できる場合もあるため、見積もり時にオプション対応が可能かを確認し、保証の手厚さとコストのバランスを見極めることが肝心です。
大規模修繕会社選びのポイント3.過去の実績・トラブル事例の有無
保証制度が整っていても、過去に誠実な対応をしてこなかった施工会社では意味がありません。実績や施工後のトラブルへの対応履歴、管理組合からの評価などを事前にリサーチしましょう。
口コミや施工実績紹介、場合によっては過去の顧客に問い合わせを行うのも有効です。保証内容そのものと同じくらい、「保証を実行する誠実さ」が重要な判断材料です。
大規模修繕会社選びのポイント4.保証対象外の条件の確認
保証には必ず「対象外」のケースが存在します。自然災害や経年劣化による損傷、居住者の管理不備が原因のトラブルなどは、多くの場合、保証適用外です。こうした条件が契約書や保証書の免責事項に記載されているかを確認し、不明点は事前に施工会社へ確認することが重要です。
対象範囲を誤認すると、トラブル発生時に「保証されると思っていたのに」といった不満が残ります。
大規模修繕会社選びのポイント5.担当者の説明力と対応力
保証制度を適切に理解・活用するためには、施工会社の担当者が制度内容を分かりやすく説明できるかどうかも重要です。曖昧な説明や回答の不一致がある場合、契約後の対応も不安が残ります。事前の打ち合わせで、具体的な保証事例を挙げて説明できるか、質問に対して的確に回答できるかを確認し、信頼できるパートナーかどうかを見極めましょう。
説明が明確な担当者を選ぶことが、安心につながります。
大規模修繕の保証トラブル事例を紹介
実際に起きた保証トラブルの事例を知ることで、契約時に注意すべきポイントが明確になります。ここでは、よくあるトラブルの具体例をいくつかご紹介します。
- 保証内容の曖昧さによるトラブル
- 口頭説明のみで書面がないケース
- 施工会社の倒産による保証消失
- 免責条件を理由に保証対象外とされる
詳しくみていきましょう。
大規模修繕の保証トラブル事例1.保証内容の曖昧さによるトラブル
保証トラブルで最も多いのが、「保証内容が曖昧で対応してもらえない」というケースです。たとえば「外壁のひび割れは保証対象外」と言われたり、「塗膜の剥がれは経年劣化」と判断されたりするなど、契約書や保証書に明記されていない内容は、後から主張しても施工会社と認識が合わず、対応を断られることがあります。
事前に書面で保証対象・範囲・条件を明記してもらうことが不可欠です。
大規模修繕の保証トラブル事例2.口頭説明のみで書面がないケース
「営業担当者が大丈夫だと言っていた」としても、書面に記載がなければ保証として成立しません。口頭説明だけに頼って契約を進めた結果、「そんな説明はしていない」とトラブルに発展することがあります。
すべての重要事項は保証書や契約書に明文化してもらい、署名を取り交わしておくことがトラブル防止の基本です。
大規模修繕の保証トラブル事例3.施工会社の倒産による保証消失
保証期間内であっても、施工会社が倒産・廃業してしまえば、保証を受ける術がなくなるリスクがあります。このような事態を避けるためにも、施工会社が「瑕疵保険」や「完成保証制度」に加入しているかを確認しましょう。これらの制度により、万が一の際にも保険会社や保証機関が補修を引き受けてくれるため、リスクを大幅に軽減できます。
大規模修繕の保証トラブル事例4.免責条件を理由に保証対象外とされる
自然災害や住民の不適切な使用、定期点検を怠ったことなどを理由に「保証対象外」とされることがあります。保証書には免責事項が細かく記載されていることが多いため、契約前に必ず確認するようにしましょう。必要に応じて、免責事項の削除や調整を交渉することも検討すべきです。
トラブルを防ぐためには、契約前の確認と記録の保存が重要です。保証内容の明記はもちろん、工事中の写真記録や引き渡し時の報告書、定期点検の実施記録を残しておくことで、保証請求時の重要な証拠となります。
また、万が一の対応に備え、工事のアフターサービス体制や問い合わせ窓口も確認しておくと安心です。
大規模修繕の保証に関するよくある質問(FAQ)
大規模修繕に関する保証制度は複雑で分かりにくい部分も多く、住民や管理組合が不安を感じやすいポイントです。ここではよくある疑問に分かりやすくお答えします。
Q
瑕疵保険と完成保証制度の違いは何ですか?
A
瑕疵保険は、工事完了後に見つかった欠陥を保険会社が修補する制度であり、完成保証制度は施工会社が工事を完了できない場合に工事の継続を保証する制度です。対象範囲とタイミングが異なります。
Q
保証制度はすべての修繕工事に適用されますか?
A
適用される保証制度は施工会社や契約内容によって異なります。必ず契約時に保証の有無と条件を確認しましょう。特に完成保証制度は、業者が該当制度に加盟していない場合は適用されません。
Q
保証期間が終了した後に不具合が発生した場合はどうなりますか?
A
原則として無償対応は受けられませんが、状況や業者によっては善意対応が行われることもあります。また、修繕積立金の活用や再修繕の検討も必要です。
Q
保証内容に納得できない場合、どうすればよいですか?
A
契約前の段階で交渉し、保証書や契約書の内容を見直してもらいましょう。不明点は専門家(管理会社・コンサルタントなど)に相談するのも有効です。
Q
保証が切れた後の再保証は可能ですか?
A
通常の延長保証はありませんが、再修繕契約を結ぶことで新たに保証対象となる場合があります。再工事の際には新たな保証内容を確認しましょう。
大規模修繕工事の保証についてまとめ
大規模修繕において保証制度は、住民の安心と資産価値を守るために不可欠な仕組みです。瑕疵保険や完成保証制度といった外部保証制度の活用や、契約書による保証条項の明記は、施工後のトラブルを未然に防ぐ大きな力になります。
保証の有無や内容だけでなく、説明する担当者の対応力、第三者保証制度の有無、そして過去の対応実績まで含めて判断することが、賢い管理組合運営の第一歩です。費用やスケジュールと同じくらい、保証という視点を重視した修繕計画を立てましょう。
大規模修繕は新東亜工業がおすすめ!
中間マージン0だから他社より安い費用で工事が可能!!
※中間マージン=仲介手数料
- 大規模修繕工事
- 解体工事
- 防水工事
- 外壁塗装
- 屋根工事
- シーリング工事
- 長尺シート工事
- 下地補修工事
- 足場工事
- タイル工事
- 洗浄工事
- 電気、水道、外溝工事等
大きな強みは「自社で完結」
施工価格と見積りには絶対的な自信を持っていますので、他社との相見積りも大歓迎です。
ご予算と現場調査の結果、長期的な視点での資産価値向上をバランスよく考慮し、お客様にとってベストな選択肢をご提案します。
建物や住宅でお困りごとがありましたら、満足度98%の新東亜へぜひご相談ください!