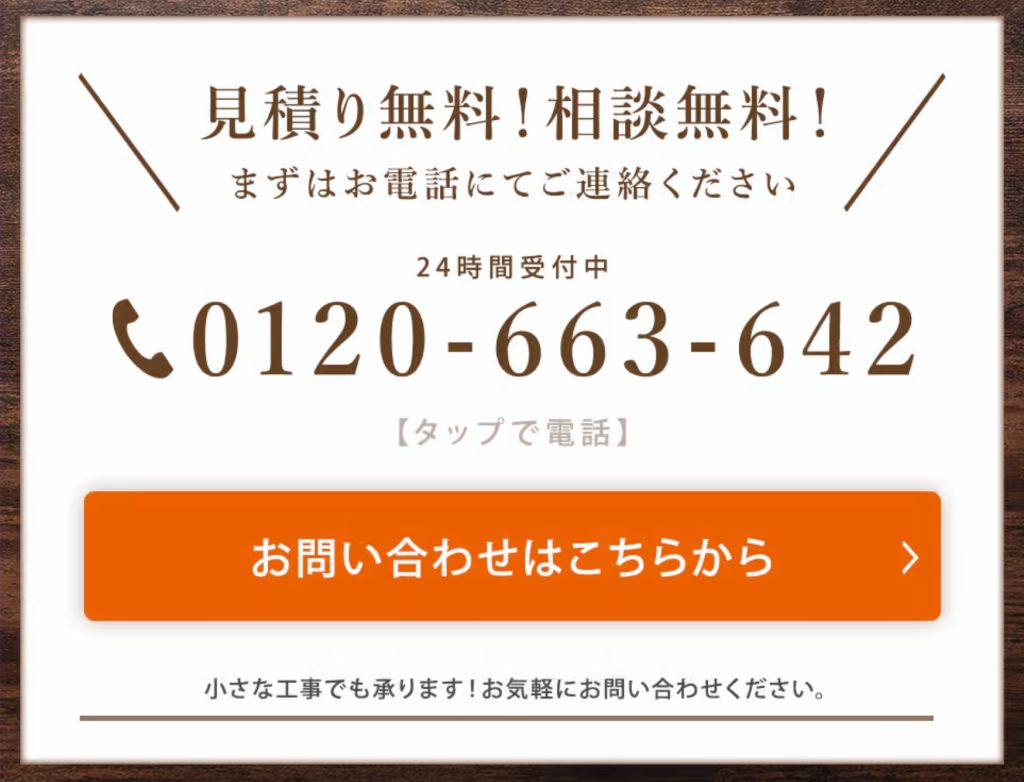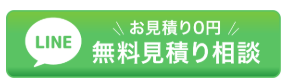防水工事を検討する際に、まず気になるのは「費用がどれくらいかかるのか」という点ではないでしょうか。施工範囲や防水の種類、建物の状態によって価格には大きな差があるため、相場を知らずに業者の見積もりをそのまま受け入れるのは避けたいところです。
屋上・ベランダ・屋根など、部位ごとに適した防水工法があり、工法によって単価や耐久性も異なります。正しい知識を身につけて、自宅に最適な防水工法を選ぶことが大切です。
この記事では代表的な防水工事の種類やそれぞれのメリット・デメリット、費用相場の目安をわかりやすく解説します。また工事費用の内訳やその比率、費用を抑えるためのポイントについても詳しく取り上げます。
予算内で安心して工事を進めるための参考情報として、ぜひご活用ください。
防水工事とは?基礎知識と必要な理由について解説
防水工事とは、建物の内部に水が侵入しないようにするための施工で、屋上やベランダ、外壁、屋根などに防水材を使って保護層を形成する工事のことです。建物は常に雨や風、紫外線にさらされており、時間の経過とともに劣化が進んでいきます。とくに日本のような高温多湿の環境では、防水層の劣化が早く、適切なタイミングでの補修や改修が不可欠です。
防水工事が必要な理由は以下のとおりです。
- 雨水や湿気の侵入を防ぎ、建物内部の腐食やカビの発生を防止するため
- 建物の構造体(鉄骨・木材など)を長持ちさせ、資産価値を維持するため
- 雨漏りによる居住環境の悪化や修繕費用の増大を未然に防ぐため
防水工事を怠ると、雨水が建物内部に浸入し、天井や壁のシミ・腐食・カビの原因となるほか、建物の構造自体を損なう可能性があります。そのため、定期的な点検とメンテナンス、そして必要に応じた防水工事が、建物の寿命を延ばすためには欠かせません。
防水工事が必要になる建物の劣化症状|早期に見つけて費用を抑えよう!
以下のような劣化サインが見られる場合、防水工事を検討するタイミングです。
- 屋上やベランダにひび割れが見られる
- 防水塗膜が剥がれて下地が露出している
- 雨上がりに天井や壁に雨染みや水滴が出る
- コーキング(目地材)が硬化・ひび割れしている
これらの症状は、放置すると雨水が建物内部に浸入し、木部や鉄骨の腐食・カビ・シロアリの原因にもなります。
防水工事の対象となる部位(屋上・ベランダ・外壁・屋根など)
防水工事の対象となる主な部位は以下の通りです。
- 屋上:フラットな屋根部分で雨水の排水が滞りやすいため、定期的な防水工事が必要
- ベランダ・バルコニー:生活空間に近く、雨水の跳ね返りや排水不良で劣化しやすい箇所
- 外壁:塗膜防水やシーリングによって雨水の侵入を防止
- 屋根(勾配屋根・折板屋根):トタンやガルバリウムなどの屋根材に応じて防水材を施工
このように、防水工事は見た目だけでなく、建物全体の健全性を守るための基礎工事といえます。
防水工事の種類とメリット・デメリット|工法別に紹介!
防水工事には、施工箇所や建物の構造、使用条件に応じてさまざまな種類があります。安価なものから高額なのもまで費用もことなるため、劣化に適した種類の判断が必要となります。
代表的な工法には、以下のようなものがあります。
- ウレタン防水
- シート防水
- FRP防水
- アスファルト防水
それぞれの特徴やメリット・デメリットについて、詳しくみていきましょう。
防水工事の種類1.ウレタン防水|柔軟性が高く万能な費用削減型
ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を塗布し、乾燥させて防水層を形成する工法です。複雑な形状にも対応でき、継ぎ目のない仕上がりが特徴です。比較的安価で施工できるため、戸建てや中小規模の建物に多く採用されています。
- 耐用年数:約10〜13年
- メリット:施工がしやすく、下地を選ばない/費用が抑えやすい
- デメリット:紫外線や熱に弱く、定期的なトップコートが必要
防水工事の種類2.シート防水|高耐久でメンテナンス性に優れる
シート防水は、塩ビシートやゴムシートを接着または機械的に固定して防水層を作る工法です。施工が速く、安定した品質が得られるのが魅力です。工場やマンションの屋上など、広面積に向いています。
- 耐用年数:約12〜20年
- メリット:耐久性が高く、メンテナンスも簡単/施工時間が短い
- デメリット:下地の形状が複雑だと施工が難しい
防水工事の種類3.FRP防水|軽量・強靭でベランダ向き
FRP(繊維強化プラスチック)防水は、樹脂にガラスマットを組み合わせた強固な防水層を作る工法です。硬化が早く、軽量で耐久性にも優れているため、戸建てのベランダやバルコニーで多く使用されます。
- 耐用年数:約10〜15年
- メリット:耐摩耗性・耐水性に優れ、軽量で工期が短い
- デメリット:下地の伸縮に弱く、ひび割れのリスクがある
防水工事の種類4.アスファルト防水|高耐久だが工期とコストに注意
アスファルト防水は、加熱溶融したアスファルトをフェルトなどに何層も重ねて施工する工法です。耐久性が非常に高く、公共施設や大型建物の屋上で多く使われていますが、工期が長くなりがちで臭気も出ます。
- 耐用年数:約15〜25年
- メリット:耐久力が高く、長期的な防水性に優れる
- デメリット:施工に手間がかかり、コストと工期がかさむ
建物の状況や予算、耐用年数などを踏まえて、最適な工法を選ぶことが大切です。以下より、わかりやすく表にまとめているので、参考にしてみてください。
| 工法 | 特徴 | 耐用年数 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| ウレタン防水 | 液体状の樹脂を塗布。継ぎ目のない仕上がりが可能 | 約10〜13年 | 柔軟性があり複雑な形状にも対応/比較的安価 | 紫外線・熱に弱くトップコートが必要 |
| シート防水 | 塩ビやゴムのシートを接着。施工が早く広面積に適す | 約12〜20年 | 耐久性が高く品質が安定/メンテナンスが簡単 | 複雑な形状には不向き |
| FRP防水 | 樹脂+ガラスマットで形成。硬化が早く強靭 | 約10〜15年 | 軽量・強靭でバルコニーに最適/工期が短い | 下地の動きに弱く、ひび割れリスクがある |
| アスファルト防水 | アスファルトを多層重ねて施工。高耐久だが臭気あり | 約15〜25年 | 長期耐久性があり公共施設向き | 工期・コストがかさみ、施工に手間がかかる |
防水工事の費用相場の目安|建物・場所・面積別などの費用も紹介!
防水工事にかかる費用は、施工面積や建物の種類、施工場所によって異なります。ここでは、面積別や建物の種類別、施工箇所ごとなどの費用相場を詳しく紹介します。
防水工事の費用相場|ウレタン防水などの工法別
防水工事にはさまざまな工法があり、それぞれ費用や特徴に違いがあります。主要な防水工法ごとの単価や特長を以下にまとめました。
| 工法 | ㎡単価 | 特徴 |
|---|---|---|
| ウレタン防水 | 約4,000〜7,000円 | 下地になじみやすく、複雑な形状にも対応可能。防水塗装との併用で効果アップ。 |
| シート防水 | 約5,000〜8,000円 | 耐久性が高く施工ムラが少ない。雨漏り対策に効果的。 |
| FRP防水 | 約6,000〜9,000円 | 硬化が早く、強度に優れる。ベランダやバルコニーのリフォームに最適。 |
| アスファルト防水 | 約6,500〜10,000円 | 耐久性・防水性能が高く、大規模施設の屋上向き。 |
防水工事の費用相場|戸建て・マンション・ビルなど建物タイプ別
| 建物タイプ | 主な施工箇所 | 費用相場の目安 |
|---|---|---|
| 戸建て | ベランダ・屋上 | 約10万円〜30万円程度 |
| マンション | 共用部・屋上 | 約100万円〜500万円程度 |
| ビル | 屋上・外壁・共用部など | 約300万円〜1,000万円以上 |
共用部が多くなるほど施工範囲が広がり、仮設足場や諸経費も増えるため、費用は高額になりがちです。
防水工事の費用相場|屋上・ベランダ・外壁など箇所別
| 施工箇所 | 費用相場 |
|---|---|
| 屋上防水 | 約40万〜120万円 |
| ベランダ防水 | 約8万〜30万円 |
| 外壁防水(シーリング含む) | 約30万〜100万円 |
使用する材料や劣化状態によって大きく異なるため、現地調査が重要です。
防水工事の費用相場|施工面積別の費用相場(10㎡・30㎡・100㎡の目安)
| 面積 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 10㎡ | 約8万〜15万円 | 小規模施工に適応 |
| 30㎡ | 約20万〜40万円 | 戸建て住宅の屋上やベランダに多い |
| 100㎡ | 約50万〜100万円 | マンション・ビルの屋上に多い |
面積が広くなるほど、㎡単価は割安になる傾向があります。ただし、工法や場所、下地の状態によって大きく変動します。
防水工事にかかる費用の内訳と注意点
見積書を見ても「何にどれだけかかるのか」が分かりづらいことがあります。材料費・人件費・諸経費など、費用構成の内訳を把握しておくことで、妥当な価格かどうかを判断できます。
防水工事にかかる費用の内訳|材料費・人件費・諸経費などの比率
以下は、一般的な防水工事における費用の内訳とその比率の目安です。
| 費用項目 | 割合の目安 | 内容例 |
|---|---|---|
| 材料費 | 約30〜40% | 防水塗料、シート、プライマー、トップコートなど |
| 人件費 | 約40〜50% | 職人の作業賃・施工手間・養生作業など |
| 諸経費 | 約10〜20% | 管理費、現場交通費、工具代など |
| 足場代 | 別途(500〜1,000円/㎡) | 高所作業時に必要。工期や規模によって増減あり |
| 下地補修費 | 状況により別途発生 | ひび割れや雨漏りがある場合に追加で必要となる工事費用 |
詳しくみていきましょう。
材料費(約30〜40%)
防水塗料やシート、プライマー、トップコートといった施工に使用される材料にかかる費用です。工法や材料の性能によって金額は上下します。耐久性が高く高品質な材料ほど価格も高くなる傾向があります。
人件費(約40〜50%)
職人による施工費が該当し、防水工事費用の中で最も大きな割合を占めます。施工の質や工期に影響するため、価格だけでなく技術力の高い業者を選ぶことが重要です。
諸経費(約10〜20%)
管理費や交通費、資材搬入費、保険料などが含まれます。現場の場所や規模、工程の複雑さによって変動するため、詳細が明記された見積もりが必要です。
足場代(別途500〜1,000円/㎡)
高所作業では安全性確保のために足場が必須です。設置面積や高さによって費用が変わりますが、全体費用へのインパクトが大きいため要確認項目です。
下地補修費(状況により別途発生)
防水層の下にあるコンクリートやモルタルが劣化している場合、その補修が必要となります。ひび割れや欠損の範囲によっては、想定以上の費用になるケースもあります。
足場代や下地補修費は条件によって大きく変動するため、見積もり時に明細として確認することが重要です。特に高所や劣化が進んだ建物では、想定以上の費用がかかることもあります。
保証年数と費用のバランスを比較しよう
安価な工事は短期的に見ればお得でも、保証年数が短い場合は再施工のリスクもあります。費用と保証内容はセットで判断を行いましょう。
防水工事の費用を抑えるためのポイント
防水工事の質を保ちながら費用を抑えるためには、事前準備と判断力が欠かせません。ここでは、コストを抑える具体的な方法を紹介します。防水工事の費用を抑えるためのポイントは以下の3つです。
- 複数社から相見積もりを取る
- 工事の適切なタイミングを見極める
- 長期的なメンテナンス視点で工法を選ぶ
防水工事の費用を抑えるためのポイント1.複数社から相見積もりを取る
防水工事の費用を抑えるうえで最も有効なのが、複数の業者から見積もりを取って相場を把握しながら比較することです。単に価格を比べるのではなく、見積もりの内訳や工事範囲、保証内容などの条件も確認しましょう。業者によっては防水塗装や雨漏り修理などをセットで提案するケースもあり、内容次第では割安になることもあります。相見積もりを取ることで、不当な高額請求を防ぎ、納得のいく工事を実現しやすくなります。
防水工事の費用を抑えるためのポイント2.工事の適切なタイミングを見極める
防水工事は、劣化が進行する前の適切なタイミングで施工することが重要です。防水層のひび割れや剥がれを放置すると、下地補修や雨漏り対応といった追加工事が必要になり、費用がかさむ原因となります。早めにメンテナンスを行えば、補修費用を最小限に抑えられ、防水工事全体の費用負担も軽減できます。劣化状況を見ながら、相場に合った適正な施工時期を見極めることがカギです。
防水工事の費用を抑えるためのポイント3.長期的なメンテナンス視点で工法を選ぶ
防水工事にかかる費用は初期費用だけでなく、今後のメンテナンスコストにも影響します。短期的な金額だけでなく、耐用年数や再施工のサイクルも加味して工法を選ぶことが大切です。たとえばアスファルト防水は初期費用が高めでも、長期間の防水性能が期待できるため、トータルで見るとコストパフォーマンスに優れています。防水工事の相場と将来的な費用負担の両方を意識して選択しましょう。
防水工事の見積もりで確認すべきチェックポイント|費用計上に注意!
見積もり書は、防水工事の信頼性や費用の妥当性を判断するための重要な資料です。記載内容が曖昧だったり、工事項目が「一式」表記のみの場合は、工事内容が不透明で後々のトラブルにつながることもあります。
ここでは、防水工事の見積もりで確認すべき主要なポイントを詳しく解説します。
防水工事の見積書に記載されるべき項目一覧
- 工法の種類:ウレタン・シート・FRPなど、どの防水工法を採用するか明記されているか
- 面積と単価:施工面積(㎡)と単価が明記されており、全体費用の計算根拠がわかるか
- 材料名と数量:使われる防水材やプライマーなどの名称・数量が記載されているか
- 保証内容:保証期間や対象範囲(防水層の破損・雨漏り等)に関する明記があるか
- 工期と作業工程:工事開始日・終了予定日、各工程の内容と順序の記載があるか
工法の種類
防水工事には、ウレタン防水・シート防水・FRP防水など複数の工法が存在します。見積書には、どの防水工法を採用するかが明記されていることが重要です。工法によって耐用年数や施工費用、適した施工箇所が異なるため、明確な記載がなければ内容を確認し、適正な工法が提案されているかを判断しましょう。
面積と単価
施工する部位の面積(㎡)と、それに対する㎡単価が見積書に明記されていることが必須です。これにより、工事全体の費用計算の根拠が明確になり、他業者との相場比較もしやすくなります。面積と単価の両方が記載されていない見積もりは注意が必要です。
材料名と数量
見積書には、防水工事に使用する材料名(防水材・プライマー・トップコート等)と、それぞれの使用数量が記載されているべきです。これにより、どのような材料がどれだけ使用されるのかが明確になり、工事の品質を推測する手がかりにもなります。
保証内容
防水工事には保証制度があるのが一般的です。保証の有無、期間、保証範囲(雨漏り・防水層の剥離など)が明記されているか確認しましょう。万が一のトラブルに備えて、保証内容は契約前に必ずチェックすることが大切です。
工期と作業工程
工事の開始予定日と完了予定日、さらに各工程(下地処理、防水層施工、トップコートなど)の流れが記載されていると、施工のスケジュールや所要日数が把握できます。スケジュールが明記されていない場合は、工期延長や未完工のリスクにつながるため、確認しておきましょう。
これらが明記されている見積もりは、工事の透明性が高く、安心して発注できる基準のひとつです。
防水工事の見積もり「一式」表記の注意点
「防水工事一式」や「材料費一式」といった曖昧な記載は、具体的な内容がわからず、後で追加費用が発生する可能性があります。とくに高額な工事の場合は、内訳を詳細に記載してもらうよう依頼しましょう。
数量・単価・施工内容を明確にすることで、費用相場と比較しやすくなり、適正価格かどうか判断できます。
防水工事の相場より安すぎる場合のリスク
相場と比べて極端に安い見積もりには注意が必要です。人件費や材料を削っている場合、施工不良や早期劣化につながる恐れがあります。
また、安さを売りにする業者の中には保証制度がなかったり、施工後のアフターサポートが不十分なケースも考えられるため、価格だけで判断せず、施工実績・口コミ・保証の有無なども総合的に確認することが大切です。
防水工事の流れについて解説|代表的なウレタン防水・シート防水の場合
防水工事は、建物の構造や状況に応じて工法や工程が多少異なるものの、一般的には以下のような流れで進行します。代表的なウレタン防水やシート防水の場合の工程をわかりやすくまとめました。
- STEP
現地調査・劣化診断
最初に専門業者が現地調査を行い、屋上やベランダの状態、ひび割れや雨漏りの有無などを確認します。劣化の進行状況に応じて、必要な工法や補修内容が決まります。
- STEP
見積もり提出と契約
調査結果に基づいて、使用する防水材、施工面積、工期、保証内容などが記載された見積書が提出されます。内容に納得すれば契約を結びます。
- STEP
施工前準備・足場設置
工事開始前に、安全に作業を行うための足場や養生を設置します。マンションやビルの場合は、近隣へのあいさつや注意喚起も行われます。
- STEP
下地処理
防水材を施工する前に、既存の防水層の撤去、ひび割れ補修、清掃などを行い、下地を整えます。この工程が不十分だと、防水効果が長持ちしない恐れがあります。
- STEP
防水層の施工
選定した工法(ウレタン防水・シート防水など)に基づいて、プライマー塗布、防水材の塗布または貼り付け、乾燥といった工程を行います。ウレタンの場合は複数回の塗布を行い、一定の厚みを確保します。
- STEP
トップコート仕上げ
紫外線や熱、摩耗から防水層を保護するために、表面にトップコートを塗布します。耐久性を高める重要な工程です。
- STEP
完了検査・引き渡し
施工完了後に業者と施主で最終確認を行い、問題がなければ工事完了となります。保証書の発行やアフターフォローについての説明もこの段階で行われます。
一連の流れを把握しておくことは極めて重要です。スケジュール管理もしやすくなり全体的な費用などのコスト削減にもつながるでしょう。
新東亜工業における防水工事の施工事例
ここでは、新東亜工業における防水工事の施工事例をご紹介します。


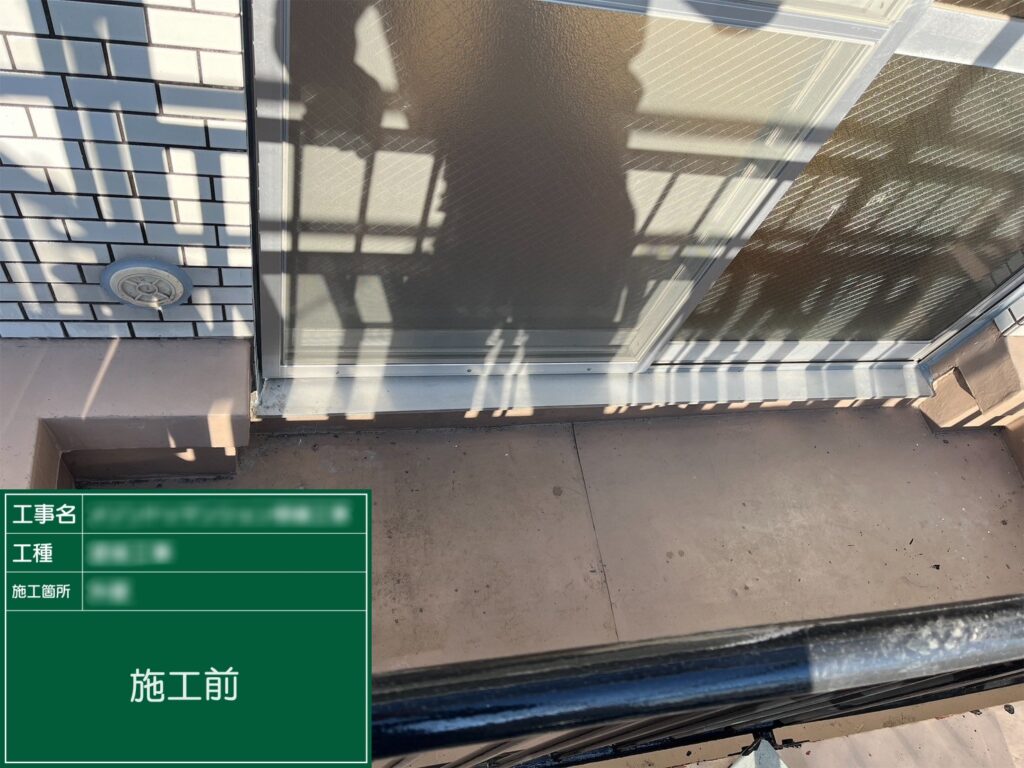

防水工事の助成金や補助金を解説|費用を軽減できるケースがあるの?
防水工事は高額になりやすい工事のひとつですが、一定の条件を満たすことで、自治体からの助成金や補助金を受けられる場合があります。
補助金制度は自治体によって異なり、耐震改修・省エネ改修・長寿命化工事の一環として防水工事が対象になるケースが一般的です。
防水工事の助成金や補助金における具体的な対象工事と補助率の例
たとえば、「屋上防水」「ベランダの防水補強」「外壁の防水修繕」などが補助対象になる場合があります。補助率は工事費用の10〜50%程度で、上限額は自治体により異なります。
多くは10万〜50万円の範囲で設定されており、申請には事前審査や図面・見積書の提出が必要です。
防水工事の助成金や補助金の申請手続き
補助金の申請には、工事前の申し込みが原則です。自治体によっては受付期間が決まっているため、リフォームを計画する際には早めに市区町村のホームページなどで情報を確認しましょう。
必要書類には申請書、見積書、現地写真、工事図面などが求められます。
防水工事で国の制度が使えるケースもある
自治体だけでなく、国が実施する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」や「住宅省エネキャンペーン」などの制度に該当すれば、防水工事も助成対象になることがあります。
特に断熱・省エネ性能と関連づけて実施する防水工事は、補助の対象になりやすい傾向にあります。
補助金対応に強い防水工事業者に相談するのが安心
補助金制度は複雑で手続きも煩雑なため、申請経験が豊富な業者に依頼することで手続きがスムーズになります。防水工事の見積もり時点で「補助金活用を検討している」と伝えると、申請サポートや対象工事の調整も可能です。
補助金の活用により、防水工事にかかる費用負担を大きく軽減できる可能性があるため、早い段階から情報収集を行い、制度の活用を視野に入れたリフォーム計画を立てましょう。
防水工事の費用相場でよくある質問(FAQ)
防水工事に関してよく寄せられる疑問を、わかりやすくQ&A形式で解説します。施工タイミングやDIYとの違いなど、気になるポイントを確認しましょう。
Q
防水工事の費用相場はいくらくらい?
A
一般的な住宅の場合、ベランダは10万〜30万円、屋上は30万〜100万円程度が相場です。マンションやビルなど規模が大きい建物では100万円〜数百万円以上かかることもあります。
Q
防水工事は何年ごとに必要?
A
工法によりますが、10年〜15年が目安です。定期的な点検も重要です。
Q
雨漏りがある場合、費用は高くなる?
A
下地補修が必要になるため、費用は高くなる傾向にあります。
Q
DIYと業者施工でどれくらい費用差がある?
A
DIYの方が安く済みますが、防水性・耐久性に不安が残るため、基本的には業者施工を推奨します。
Q
見積もりは無料で取れるの?
A
多くの防水工事業者では、現地調査を含む見積もりを無料で行っています。事前に費用が発生するか確認することをおすすめします。
防水工事の費用相場まとめ|適正価格で安心できる防水工事を
防水工事の費用相場とその内訳を理解することで、後悔しない工事選びができます。信頼できる業者と連携し、長期的に安心できる住環境を目指しましょう。
防水工事の費用は、工法や施工箇所、建物の状況によって異なります。まずは相場を把握し、信頼できる業者に相見積もりを取ることが成功の第一歩です。安さだけに惑わされず、保証や施工品質をしっかり見極め、長く安心できる防水工事を目指しましょう。
地域によっては助成金や補助金が活用できる場合もあるので、事前に情報収集しておくことも大切です。
大規模修繕は新東亜工業がおすすめ!
中間マージン0だから他社より安い費用で工事が可能!!
※中間マージン=仲介手数料
- 大規模修繕工事
- 解体工事
- 防水工事
- 外壁塗装
- 屋根工事
- シーリング工事
- 長尺シート工事
- 下地補修工事
- 足場工事
- タイル工事
- 洗浄工事
- 電気、水道、外溝工事等
大きな強みは「自社で完結」
施工価格と見積りには絶対的な自信を持っていますので、他社との相見積りも大歓迎です。
ご予算と現場調査の結果、長期的な視点での資産価値向上をバランスよく考慮し、お客様にとってベストな選択肢をご提案します。
建物や住宅でお困りごとがありましたら、満足度98%の新東亜へぜひご相談ください!