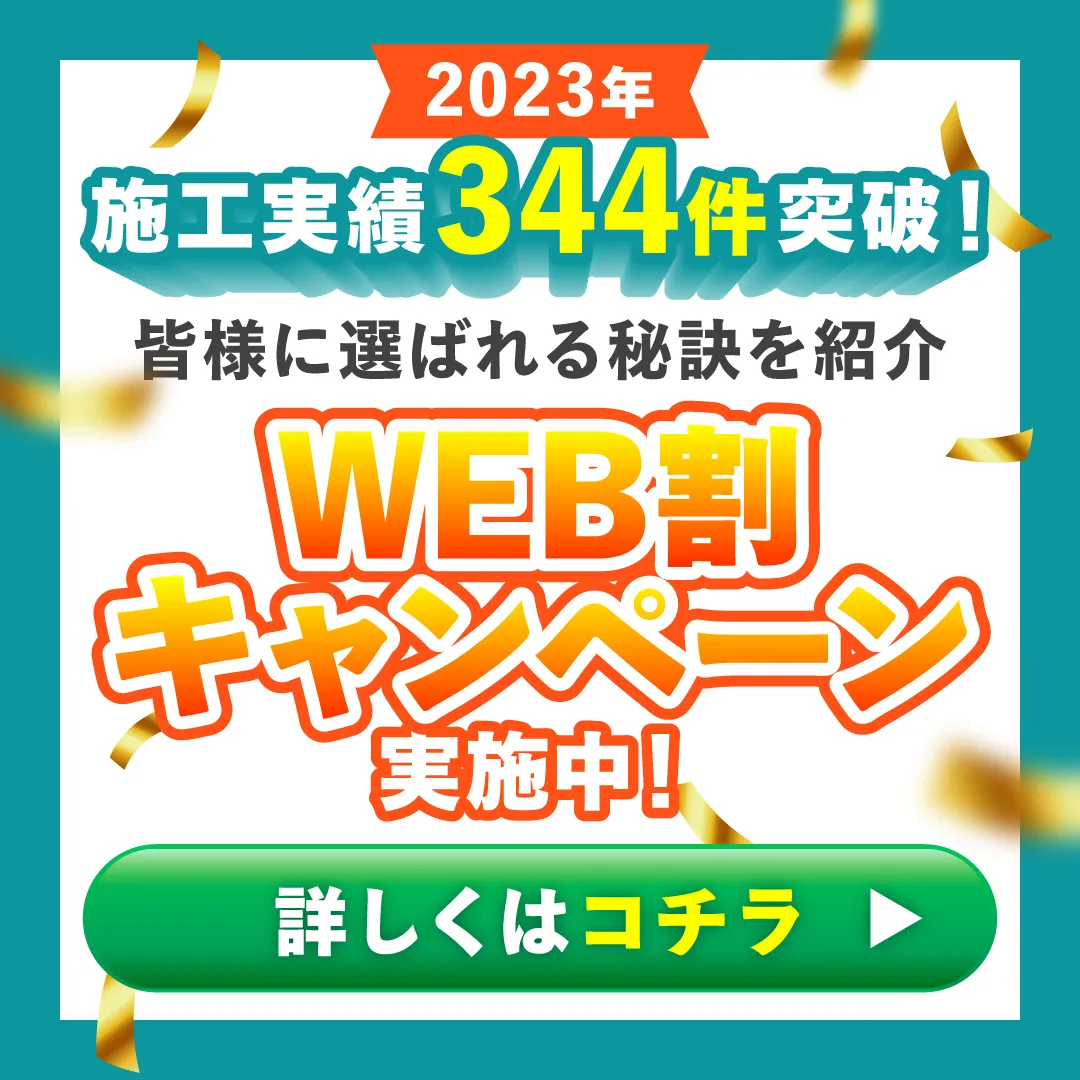マンションやビルといった集合住宅は、年月とともに外観や設備が劣化し、機能や安全性・美観が損なわれていきます。
これらをまとめて補修・改修するのが「大規模修繕」です。
外壁のひび割れや防水層の劣化・鉄部のサビ・設備の老朽化などは、放置すれば大きなトラブルを引き起こします。
大規模修繕は、単に建物をきれいにするだけでなく、資産価値を守り、居住者が安心・快適に暮らせる環境を維持するために不可欠な取り組みです。
大規模修繕・防水工事・外壁塗装なら
新東亜工業へ!
マンション修繕の顧客満足度98%
マンション・アパート・ビルの大規模修繕や防水工事の最適な工法を提案し、プロの技術で安心した施工をお約束!
- 自社施工で高品質な仕上がり
- 中間マージンを排除、適正価格を実現
- 大規模修繕・防水工事の豊富な実績
- 最長10年の保証付、安心のアフターフォロー
- 関東エリアを中心に幅広い地域へ対応
\中間マージン0だから他社よりも低コスト/
目次
大規模修繕の目的
大規模修繕における最大の目的は、建物の性能回復や寿命の延命です。
年月が経つと、外壁・屋上防水・鉄部・シーリング・共用設備などは必ず劣化します。
このまま放置すると雨漏りや外壁落下のほか、設備の故障といった深刻な問題を引き起こし、結果的に修繕費が高騰するリスクもあります。
また、建物が古びて見えると資産価値が下がり、空室率の増加や売却・賃貸の難航につながる恐れもあるでしょう。
そのため外観の美しさを保ち、入居者が安心して住み続けられる環境を確保することも目的の一つです。
例えば、エレベーターや共用部などにバリアフリー化の改善を行うことで、住まいの快適性や安全性向上に大きく寄与します。
大規模修繕の主な内容と詳細
外壁工事
外壁のひび割れは雨水の侵入経路となり、建物内部の鉄筋を腐食させる原因です。
また、タイルの浮きや剥離も落下事故を招く恐れがあります。
これらを補修し、外壁全体に新たな塗装を施すことで、防水性と美観を回復させるのが外壁工事です。
屋上・バルコニー防水工事
屋上は紫外線や雨風にさらされるため、防水層が徐々に劣化します。
劣化を放置すると漏水が発生し、住戸内部や構造体に深刻なダメージを与えるので、屋上・バルコニー防水工事が必要です。
屋上の防水シートや塗膜の張り替え・バルコニー床の防水施工などを行い、建物全体を水の侵入から守ります。
鉄部・金物の補修・塗装
共用部の手すりや扉・階段などの鉄部は、サビが発生しやすい部分です。
サビを放置すると部材が脆くなり、安全性が低下します。
古い塗膜を除去し、防錆処理を施した上で再塗装を行うことで、耐久性と見た目の美しさを回復させます。
シーリング工事
シーリング(コーキング)は、外壁の目地や窓枠周辺に充填されているゴム状の材料で、防水の要ともいえる部分です。
経年劣化で硬化・ひび割れが生じると防水性が失われるため、定期的に打ち替える必要があります。
共用部設備の修繕
給排水設備は、パイプの内部腐食や漏水・ポンプや受水槽の老朽化が問題になりやすい場所です。
例えば、電気設備では照明の不具合やインターホンの故障・エレベーター設備の更新などが該当します。
居住者の日常生活に直結するため、必要に応じて更新や補修を行います。
その他の共用部分における修繕
駐車場や駐輪場の白線・番号の引き直しのほか、植栽の補植と剪定・エントランスの床材や壁材の美装工事なども行われます。
細かな部分まで手を入れることで、建物全体の印象が向上し、居住者や来訪者に良い印象を与えます。
大規模修繕の流れ
大規模修繕は、マンションの資産価値を維持・向上させ、住民の安心・安全な生活を守るために欠かせない長期プロジェクトです。
計画から完了まで多くの関係者が関わり、段階ごとに丁寧な準備と管理が求められます。
以下に一般的な流れと、それぞれの段階での重要ポイントを解説します。
- STEP
建物調査・診断
まずは、現在の建物の状態を正確に把握することから始まります。
管理組合は専門業者に依頼し、外壁のひび割れ・屋上における防水層の劣化・鉄部のサビ・共用設備の機能低下などを詳しく調査します。
近年ではドローンや赤外線調査といった最新技術を使うケースも増えており、表面に見えない内部の劣化まで把握できる場合があるでしょう。
調査結果は、修繕の必要性を判断する重要な資料になるため、信頼できる診断業者を選ぶことが大切です。 - STEP
修繕計画の立案
調査結果をもとに、管理組合が修繕範囲や優先順位・実施時期・概算予算を検討します。
この段階では、修繕積立金の残高や不足額を確認し、必要であれば金融機関からの借入れや一時金徴収といった資金計画も検討されます。
住民説明会を開催し、計画内容を丁寧に説明した上で、住民の理解と合意を得ることが重要です。
ここで住民の納得を得られない場合、後々トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。 - STEP
設計・仕様の決定
管理組合が設計監理者やコンサルタントを選任し、具体的な工事内容の設計と仕様書を作成します。
例えば「防水工事にはどの材料を使うのか」「外壁塗装の色はどうするのか」といった、詳細を詰めていきます。
仕様の決定は工事費用や将来の維持管理費用に大きく影響するため、専門家の助言を活用しつつ、長期的な視点で検討を行うことが求められます。 - STEP
施工会社の選定
複数の施工会社から見積もりを取り、価格だけでなく提案内容や実績・技術力・アフターサービス・保証内容などを総合的に比較します。
プレゼンテーションを実施し、会社側の説明を直接聞くことで、管理組合が納得できるかを判断することが重要です。
また、設計監理者やコンサルタントと相談し、客観的な評価を行うことも欠かせません。
安易に最安値の会社を選ぶと後悔するケースも少なくないため、慎重な検討が必要です。 - STEP
工事契約の締結
選定した施工会社と、正式な工事契約を締結します。
契約書には、工事内容や使用材料・金額・支払い条件・工期・保証内容などが明記され、後のトラブルを防ぐための重要な書類となります。
また、詳細な工事スケジュールもここで策定され、住民に対する周知や調整が始まります。特に駐車場やバルコニー・エントランスの使用制限など、共用部分の制限は住民の生活に影響するため、事前の説明が欠かせません。 - STEP
着工・工事管理
契約の締結後、工事の開始です。
工事中の品質・安全・スケジュール管理は、設計監理者と施工会社が密に連携して行います。
管理組合は定期的な進捗報告を受け、必要に応じて現場視察を行います。
また、住民からのクレームや要望にも迅速に対応し、生活への影響を最小限に抑えるような調整が求められるでしょう。
工事期間中は仮設足場や資材搬入などで共用部の安全管理が重要となるため、日々の安全確認も欠かせません。 - STEP
工事完了・検査・引き渡し
工事が完了したら、管理組合・設計監理者・施工会社が立ち会って完了検査を実施します。
仕上がりや仕様通りに工事が行われているか、不具合や未完了部分がないかを細かく確認し、必要があれば手直しを依頼します。
最終確認が済んだ後に正式な引き渡しとなり、保証書や完成図書の受け渡しが行われます。住民には改めて工事完了を周知し、今後のメンテナンス計画や保証内容を共有することで、修繕後の安心感を高めます。
何年目にどのような工事が必要か?
マンションやビルといった集合住宅は、年月とともに建物や設備の劣化が進行します。
これらを放置すると、見た目の悪化だけでなく雨漏りや安全性の低下、設備の故障といった深刻な問題につながるため、計画的な修繕が欠かせません。
一般的な修繕スケジュールの目安を紹介します。
築5~10年目
この時期は、外壁のひび割れや防水層の軽微な劣化・鉄部のサビといった小規模な劣化が目立ち始める頃です。
まだ大規模修繕の必要はありませんが、劣化を放置すれば後の修繕費が大幅に増加するリスクがあります。
主なメンテナンス内容は、以下の通りです。
- 外壁の部分補修
- 屋上やバルコニーの防水層補修
- 鉄部(手すり・階段・門扉など)の防錆塗装
- 給排水設備の点検・軽微な補修
築12~15年目
建物全体の劣化が顕在化し、初めての大規模修繕を実施する時期です。
外壁や屋上・防水・鉄部・シーリングなど、建物を保護する外皮部分の全面改修が中心になるでしょう。
この時期の修繕は、住民の生活に直接影響を及ぼすため、住民説明会やアンケートを実施し、合意形成を図ることが重要です。
主な工事内容としては、以下が挙げられます。
- 外壁の全面補修・塗装・タイル補修
- 屋上防水工事(シート防水、塗膜防水などの全面改修)
- 鉄部塗装の全面改修
- 窓まわり・建物目地のシーリング材打ち替え
築25~30年目
第1回と同様の範囲に加え、共用設備の老朽化が目立つようになる時期です。
特に給排水管や電気設備・エレベーターなどの更新が必要になることが多く、放置すると設備トラブルや事故のリスクが増加する恐れがあります。
また、設備の更新は多額の費用がかかるため、修繕積立金だけでは不足する場合もあり、注意が必要です。
一時金徴収や借入れの計画を早めに立て、住民と協議することが求められます。
2回目の大規模修繕では、以下のような工事を行うことが多いです。
- 第1回と同様の外皮部分の全面改修
- 給排水管(共用部分)の更新・更生工事
- 電気・通信設備の更新
- エレベーター設備の更新・制御装置の改修
築40年以上
建物の構造体や耐震性能、主要設備の全面更新が検討される時期です。
築40年以上の建物は旧耐震基準で建設されている場合もあり、耐震補強工事が必要となるケースがあります。
また、共用部分のデザイン刷新やバリアフリー化・省エネ設備の導入など、現代のニーズに合わせた改修も検討されます。
また、単なる修繕ではなく「再生的改修」の段階に入るため、場合によっては建替えとの比較検討も必要になり、専門家の助言を受けながら慎重に進めることが求められるでしょう。
主な工事内容は、以下の通りです。
- 外皮部分の全面改修
- 耐震診断・耐震補強工事
- 給排水管・電気・ガス・空調設備の全面更新
- バリアフリー改修(手すり、スロープ設置など)
- 省エネ設備導入(LED照明、太陽光発電、断熱工事など)
修繕スケジュール目安表
| 築年数 | 修繕内容の目安 |
| 5~10年 | 部分補修(外壁ひび割れ・防水層補修・鉄部防錆塗装)、予備的メンテナンス |
| 12~15年 | 第1回大規模修繕(外壁全面改修・屋上防水・鉄部塗装・シーリング打ち替え) |
| 25~30年 | 第2回大規模修繕(1回目と同範囲+給排水管更新・電気設備改修・エレベーター更新など) |
| 40年以上 | 第3回以降の大規模修繕(耐震補強・設備全面更新・バリアフリー・省エネ化など、建替え検討も含む) |
施工会社選定時のチェックポイント
施工会社の選定は、大規模修繕の成否を大きく左右する重要なステップです。
適切な会社を選べば、工事の質や進行管理が安定し、住民の負担やトラブルが大幅に軽減されます。
逆に選定が不十分だと、工事途中のトラブル・予算超過・施工不良といった深刻な問題につながることもあります。
以下のポイントを押さえ、慎重に選定を進めることが推奨されます。
実績・経験
施工会社のこれまでの実績や経験は、信頼性を測る大きな指標です。
特に自分たちのマンションと同じ規模・構造・用途での修繕工事経験が豊富な会社を選ぶことで、予期せぬ問題に対する対応力を期待できます。
過去の施工実績を資料として提出してもらい、実際の施工レベルや仕上がりを確認するのも有効です。
技術力・提案力
価格だけで施工会社を選ぶと、トラブルにつながるリスクがあります。
重要なのは、その会社が最新の工法や材料・長期的な耐久性を見据えた最適な修繕プランを提案できるかどうかです。
例えば、ただ古い設備を取り替えるだけでなく、省エネ効果の高い材料や将来的なメンテナンス負担を軽減できる工法を提示してくれる会社は、管理組合にとって長期的な利益をもたらします。
見積内容や提案書を読み込むだけでなく、説明を受けて質問し、提案の根拠やメリットをしっかり確認しましょう。
見積内容の明確さ
見積書の内容は、素人には分かりにくい専門用語が並びがちですが、項目ごとに具体的な工事内容や使用材料・数量が明記されているかを確認することも大切です。
不明確なまま契約してしまうと、後から「これは見積に含まれていない」として追加費用が発生することがあります。
必要に応じて、設計監理者や修繕コンサルタントに見積書を精査してもらい、疑問点を事前に洗い出しておくと安心です。
保証・アフターサービス
工事が完了した後も、建物は時間とともに劣化していきます。
だからこそ工事後の保証年数や、不具合が発生した場合の対応について確認することが重要です。
例えば「防水工事の保証が10年ついているのか」「外壁塗装の剥がれに対する補償は何年なのか」といった点を明文化した書面を取り交わすことで、万一の際のトラブルを防ぐことができます。
また、アフターサービスの具体的な内容についても確認しておきましょう。
担当者の対応力
施工会社の担当者は、契約後から工事完了までの長期間、管理組合や住民と直接やり取りをするパートナーです。
見積段階の打ち合わせ時点から、こちらの質問に誠実かつ分かりやすく答えてくれるか、要望や変更点に柔軟に対応してくれるかをよく見極めましょう。
担当者の対応力は、工事が順調に進むかどうかを大きく左右する要素です。
また、管理組合内での意見調整が必要な場面では、担当者の説明力や調整力が重要な役割を果たします。
大規模修繕でトラブルを防ぐための注意点
大規模修繕は数か月から1年以上に及ぶ大規模プロジェクトです。
金額の大きさや住民生活への影響も大きいため、計画段階から慎重に進める必要があります。
以下の点を意識することで、トラブルの発生を未然に防ぐことができるでしょう。
住民間の情報共有と合意形成
修繕計画は、管理組合の理事会だけで決めて進めてしまうと、後になって「そんな話は聞いていない」「納得できない」といった住民の不満につながることがあります。
特に、修繕積立金の増額や一時金の徴収が必要な場合、住民の理解と納得が欠かせません。
説明会を開き、疑問点を解消する質疑応答の時間を設けたり、アンケートで意見を吸い上げたりするなど、できるだけ多くの住民がプロジェクトに参加していると感じられるように工夫することが重要です。
見積・契約内容の詳細確認
大規模修繕では複数の施工会社から見積を取り、比較検討しますが、単純に金額が安いからという理由だけで業者を選ぶのは危険です。
工事の範囲や使う材料の品質・工期・保証の範囲などをしっかり確認し、住民にとってベストな選択をすることが求められます。
また、後で「そんな話は聞いていなかった」とならないよう、契約内容や打ち合わせの議事録を必ず書面で残し、関係者間で共有することが大切です。
スケジュール管理の徹底
工事中は、足場設置による騒音や共用廊下やエレベーターの一時的な使用制限・駐車場の封鎖・バルコニーの使用禁止など、住民の生活に少なからず影響が出ます。
工事が長引いたり、急な予定変更があると、住民からの不満が爆発しやすくなるので注意しましょう。
事前に工事スケジュールをきちんと作成し、各住戸に通知を行うほか、必要に応じて掲示板や回覧板で随時最新情報を伝えるなど、綿密なスケジュール管理が欠かせません。
外部専門家の助言活用
管理組合のメンバーは、ほとんどが大規模修繕の素人です。
施工会社と直接交渉するのではなく、第三者である設計監理者や修繕コンサルタントといった外部専門家を間に入れることで、技術的な裏付けや公平な視点を確保できます。
専門家の存在は、施工会社とのトラブル防止や、住民説明時の信頼性向上にも役立つため、積極的に活用することをおすすめします。
管理組合の役割とは?
管理組合は、マンションの区分所有者全員で構成される組織です。
大規模修繕においては、理事会を中心に以下のような役割を担います。
- 建物調査・診断の手配:劣化状況を正確に把握するため、調査・診断の専門業者を選定し、現地調査を依頼する
- 修繕計画や予算の策定:調査結果を基に修繕範囲や予算を検討し、必要に応じて借入・臨時徴収など不足分の調達方法を話し合い計画を立てる
- 修繕積立金や資金の管理:大規模修繕は数千万円単位になることが多く、計画的に積み立てを行い、必要資金が不足しないよう長期的に管理する
- 施工会社の選定・契約手続き:複数社から見積もりを取り、工事内容・価格・実績を比較して施工会社を選定する。契約条件や保証内容の確認・契約書の取り交わしなど、細かな手続きなども行う
- 居住者への説明・協力依頼: 修繕工事中は騒音や共用部の利用制限が発生するため、住民に対する丁寧な説明と協力依頼を行う
- 工事中の進捗確認・品質管理:工事が計画通り進んでいるか、手抜きや不具合がないかを定期的に確認する
- 工事完了後の検査・引き渡し確認:工事完了後は管理組合立会いのもと検査を実施し、不備があれば補修を依頼する。問題がないことを確認してから正式に工事の引き渡しを受ける
まとめ
大規模修繕は、マンションやビルの価値を守り、住民の安全で快適な生活を維持するために欠かせない重要な取り組みです。
外壁工事や屋上・バルコニー防水工事・シーリング工事など、さまざまな工事内容が存在します。
また、マンションやビルといった集合住宅は、年月とともに建物や設備の劣化が進行するため、計画的な修繕が欠かせません。
そのため、定期的な建物調査で劣化状況を把握し、 築年数や劣化状況に応じた的確な修繕内容を実施することが大切です。
計画的で無駄のない修繕を進めることで建物は長寿命化し、資産価値を維持・向上させることにもつながります。
記事内で紹介した内容はあくまで一般的な目安であり、各建物ごとに必要な対応は異なるため、大規模修繕を検討する際は必ず専門家と相談し、最新の状況に合った計画を立てましょう。