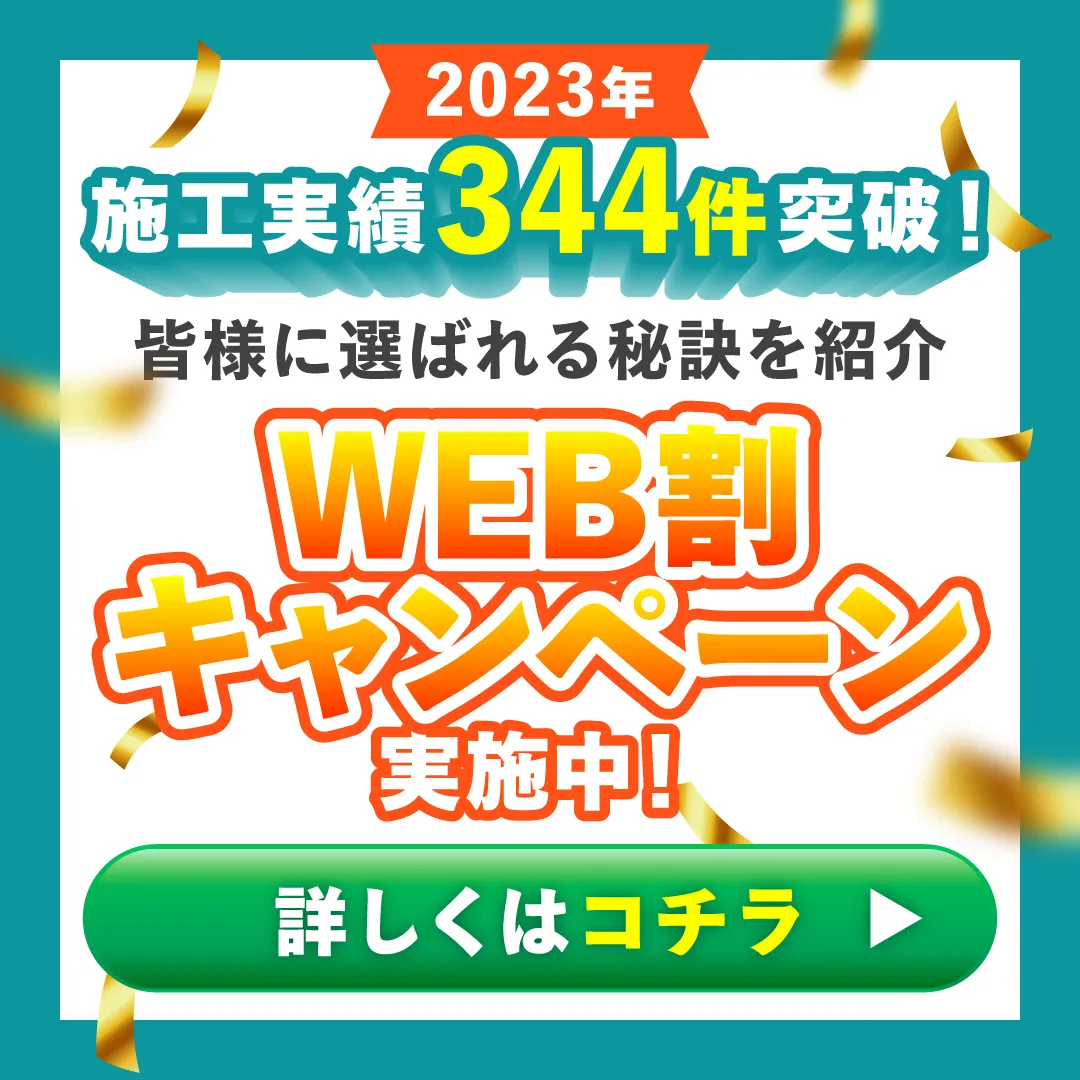マンションに長く安全に、そして快適に住み続けるために大規模修繕工事は欠かせません。
建物の機能維持と資産価値保持のために必要な工事ですが、その実施時期については「12年周期が一般的」と聞いた方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際にはマンションの状態はそれぞれ異なり、必ずしも一律の周期が当てはまるわけではありません。
本記事では、マンション大規模修繕工事の一般的な周期とされる12年周期の背景と理由、周期延長の可能性、そして何よりも重要な「適切な時期を見極めるためのポイント」について、国土交通省のガイドラインや建築基準法、建物の劣化メカニズムなどを踏まえながら詳しく解説します。
マンションの長期的な維持管理を考える一助として、記事の内容をぜひお役立てください。
大規模修繕・防水工事・外壁塗装なら
新東亜工業へ!
マンション修繕の顧客満足度98%
マンション・アパート・ビルの大規模修繕や防水工事の最適な工法を提案し、プロの技術で安心した施工をお約束!
- 自社施工で高品質な仕上がり
- 中間マージンを排除、適正価格を実現
- 大規模修繕・防水工事の豊富な実績
- 最長10年の保証付、安心のアフターフォロー
- 関東エリアを中心に幅広い地域へ対応
\中間マージン0だから他社よりも低コスト/
目次
マンション大規模修繕工事の重要性
マンションは非常に頑丈な建物ですが、日々の雨風や日射といった自然環境の影響を絶えず受け、年月とともに少しずつ変化、すなわち経年劣化が進んでいきます。
このような劣化を放置してしまうと、建物の寿命を縮めるだけでなく、居住者の安全や快適な生活が損なわれる可能性があります。
また建物の見た目が悪化したり、不具合が増えたりすることで、マンションの資産価値も低下してしまいます。
大規模修繕工事は、こうした経年劣化から建物を守るために行われる、計画的な修繕です。
具体的には、外壁や屋上・バルコニー・共用廊下といったマンションの共用部分について、傷んだ箇所を修繕したり、必要に応じて交換したりする工事をまとめて行います。
これにより、建物の主要構造部や外装材などを保護し、雨水の浸入を防ぎ、機能を回復・維持することが可能になります。
このように、大規模修繕は、マンションの機能・性能を維持し、そして何より大切な資産価値を守るために不可欠な工事なのです。
適切な時期に適切な内容の工事を行うことで、マンションに長く安心して住み続けることが可能になります。
なぜ「12年周期」が一般的とされているのか?
マンションの大規模修繕工事の周期として「12年」という数字をよく耳にするのはなぜでしょうか。
実際、多くのマンションで長期修繕計画が12年周期で設定されています。
これにはいくつかの理由が考えられます。
国土交通省の長期修繕計画作成ガイドラインの影響
大規模修繕のタイミングが12年周期とされる理由の一つに、国土交通省が公開している長期修繕計画作成ガイドラインの影響があります。
長期修繕計画は、マンションの将来的な修繕工事を見据え、向こう30年程度の間にどのような修繕工事がいつ必要になるか、そしてそれにどれくらいの費用がかかるかを細かに記載した計画表です。
これは、管理費や修繕積立金の算出根拠にもなります。
公開された長期修繕計画作成ガイドラインでは、修繕周期の考え方を示す例として、大規模修繕工事を12年程度で実施する例を紹介しています。
これは明確な周期を表したものではなく、あくまで一般的な仕様や工法・既存文献を参考に「おおよその目安として設定した」ものであり、そして「マンションの仕様、立地条件等に応じて修正します」と記載されているものの、このガイドラインが公開されて以降、多くのマンションがこのガイドラインを参考に修繕計画を作成し、12年周期が広く浸透することになりました。
特に新築の分譲マンションの場合、最初の長期修繕計画案は分譲会社が作成することが多いため、このガイドラインを参考に12年周期で設定されるケースが多く見られました。
これが、マンションの大規模修繕が12年ごとに行われることが一般化した大きな理由の一つと考えられています。
その後このガイドラインは改訂され、大規模修繕工事の周期について「部材や工事の仕様等により異なるが一般的に12年~15年程度」と示されています。
さらに改定されたガイドラインでも、大規模修繕工事は12~15年周期が実施の目安とされています。
これにより、目安とされる周期に幅が持たせられるようになりました。
建物に使用される材料の劣化タイミング
「12年周期」が多く採用されてきたもう一つの理由として、建物外部に使用される塗料や防水材などの機能・性能が低下してくる時期や、過去の大規模修繕工事で補修した箇所の保証期間が切れるタイミングを見越しているという側面があります。
外壁に使用される塗料・シーリング材・防水材・タイルといった建材は、日々雨風や日射の影響を受けていますが、高い耐久性を備えているとはいえ、10年を超えてくるとどうしても劣化の兆候(ひび割れや膨れなど)が現れ始めます。
特に塗料の寿命は約8年程度、長持ちしても12年程度と言われています。
コンクリート内部に至るような深刻な劣化を予防し、建物を長く健康に保つためには、こうした軽微な劣化の兆候が表れた早期の段階で発見し、補修することが非常に大切です。
12年という周期は、これらの主要な建材の劣化が目立ち始めるタイミングと一致しているため、予防的な観点から設定されてきたと考えられます。
特定建築物定期調査の実施時期との関連
建築基準法に基づき定められている特定建築物定期調査も、12年周期が一般的となった理由の一つです。
建物の所有者(マンションの場合は管理組合など)は、建物を適正に維持管理し安全性を確保するため、この定期報告制度に基づき専門の資格者による検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。
特に、外壁のタイルやモルタルなどの落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分については、竣工・外壁改修後・外壁全面打診等調査実施後から10年を超える場合、全面打診調査の実施と報告が義務付けられています。
さらに、マンションの外壁について3年ごとの定期報告が義務付けられています。
この全面打診調査には、多くの場合、建物の規模に応じて足場が必要となります。
大規模修繕工事もまた、外壁や共用廊下、バルコニーなどの工事を行う際に足場を設置することが一般的です。
大規模修繕工事と全面打診調査を同時に実施すれば、足場を一度組むだけで済むため、コスト効率が良いと考えられます。
このため、多くのマンションで、定期報告(特に10年を超える場合の全面打診調査のタイミング)に合わせて、概ね12年周期で大規模修繕工事を実施するという流れが定着しました。
大規模修繕工事を12~15年周期で行うことで、定期報告の要件を概ね満たすこともできます。
大規模修繕の周期延長(15年や18年など)について
近年、マンションの大規模修繕工事に使用される材料や工法は進化しており、これに伴い15年や18年といったより長いスパンで大規模修繕を計画するマンションも出てきました。
特定の管理会社や施工会社が、周期延長を提案する商品やサービスを発表しています。
周期延長の主な目的は、コスト削減です。
計画期間内でのトータルの工事回数を減らすことで、長期的なライフサイクルコストを抑制することを目指します。
例えば60年間で考えると、12年周期であれば5回の工事が必要ですが、15年周期であれば4回、18年周期であれば約3回の工事で済むことになります。
1回の大規模修繕工事には数千万から億単位の費用がかかるため、工事回数が1回減るだけでも、長期的なコスト削減効果は非常に大きいと言えます。
長期的な視点で見ると、マンション全体の維持管理コストの削減につながる効果が期待できます。
ただし、この長期的な削減効果を正確に把握するためには、60年間程度の長期修繕計画を立案して評価する必要があり、30年程度の計画期間だけでは効果を推し量ることは難しいとされています。
周期延長の注意点と課題
コスト削減のメリットがある一方で、周期延長にはいくつかの注意点と課題があります。
建物の現状を無視して計画なく周期を延ばすことは、かえって建物の劣化を早め、深刻なダメージにつながるリスクを増大させてしまう結果となりかねません。
劣化兆候を放置することで、将来的な修繕費用が大幅に増大してしまうこともあります。
周期を長くするためには、通常の大規模修繕工事よりも耐久性の高い材料や工法を採用する必要があります。
特に、防水工事や外壁塗装工事などでは、次回足場をかけるまでの期間、品質が保証されるような高耐久の部材や工法を用いることが重要です。
しかし、このような耐久性の高い仕様は、残念ながら1回当たりの工事費用が通常よりもやや割高になる傾向があります。
また、大規模修繕の間隔が延びたとしても、修繕間の軽微なメンテナンスは不可欠です。
大規模修繕工事の時期まで建物を放置するのではなく、足場を必要としない範囲での日常的な点検や、劣化の初期段階での軽微な補修などをきちんと行うことが大切です。
このようなこまめなメンテナンスを怠らなければ、周期延長はより現実的な選択肢となりえるでしょう。
さらに、大規模修繕の周期を変更する場合、それに合わせて修繕積立金の計画も見直す必要があります。
長期修繕計画と修繕積立金の整合性を確認し、将来的に必要な費用を賄えるように計画を変更する必要が生じることもあるでしょう。
計画期間全体でのコスト削減が期待できる一方で、積立金の額や徴収方法について、居住者間の合意形成が必要となる場合もあります。
周期延長の実績に基づいた提案ができる施工会社が、現状ではまだ少数派であるという現実も課題です。
高耐久性工事の実績が豊富で、周期延長を具体的に提案できる業者はまだ少ないのも実情です。
適切な大規模修繕の周期を見極めるために
「12年周期」はあくまで一般的な目安であり、大規模修繕工事の周期や回数に法律上の明確なルールや決まりはありません。
では、どうすれば自分のマンションにとって最適な時期を見極めることができるのでしょうか。
最も重要な判断基準となるのは、基本的にはマンションの実際の劣化状況です。
先に述べたように、同じ築年数でも、建物の形状や構造・海沿いか山沿いかといった環境的要因・日当たりの良い面と悪い面、そして日常の管理状況といったさまざまな要素によって劣化の進行度合いは大きく異なります。
そのため、機械的に築年数や経過年数だけで時期を決めるのではなく、個々のマンションの「今」の状態を正確に把握することが不可欠です。
建物の劣化状況を確認するための方法として「建物診断」が非常に重要です。
建物診断は、専門家が建物の外壁・屋上・バルコニー・共用廊下・設備などを詳細に調査し、ひび割れや剥がれ・浮き・錆などの劣化症状の有無や程度を確認するものです。
診断の結果、建物の現状が明らかになり、どこにどのような劣化が発生しているのか、そしてその劣化がどの程度進行しているのかを正確に把握できます。
建物診断の結果に基づき、大規模修繕工事の時期を判断することが、適切な周期を見極めるための鍵となります。
診断で緊急性の高い劣化が見つかれば早期の工事が必要になりますし、軽微な劣化に留まっていれば周期を延ばす検討も可能になるかもしれません。
建物診断の結果と、現在の長期修繕計画を照らし合わせることで、本当に計画通りの時期に工事が必要なのか、それとも前後させることが適切なのかを総合的に判断することができます。
適切な大規模修繕の周期を見極めるためには、このような建物診断を実施することから始めることを強く推奨します。
また劣化状況の確認や、その結果を踏まえた適切な周期判断、工事内容の検討などについては、専門家への相談を推奨します。
マンション管理士、一級建築士などの専門知識を持つ第三者の意見を取り入れることで、客観的かつマンションにとって最善の選択を行うことができるでしょう。
多くのマンションでは、初めての大規模修繕を控えた築10年頃から情報収集を開始し、修繕委員会の立ち上げや建物診断の実施といった準備を少しずつ始めるケースが多いようです。
大規模修繕工事の準備には、通常でも1年~2年程度の期間が必要となります。
周期延長など、検討事項が増える場合はさらに長い準備期間が必要となるため、余裕を持って早期に準備を開始することが望ましいでしょう。
長期修繕計画と資金計画
大規模修繕工事は、多額の費用がかかるため、資金計画が非常に重要になります。
その基盤となるのが長期修繕計画です。
長期修繕計画は、前述の通り向こう30年以上の期間にわたる修繕工事の計画と、それに伴う費用を盛り込んだものであり、修繕積立金の設定根拠となります。
国土交通省のガイドラインでは、計画期間は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とされています。
しかし、長期修繕計画はあくまで作成時点での「計画」であり、建物の実際の劣化状況や社会情勢の変化に合わせて、定期的な見直しが必要です。
計画通りに進まないこともありますし、想定外の劣化や修繕が必要になることもあります。
資金計画、つまり修繕積立金の計画が非常に重要なのは言うまでもありません。
計画されている大規模修繕工事や将来的な修繕に必要な費用を賄えるだけの積立金がなければ、いざ工事が必要になった際に資金不足に陥り、工事を延期せざるを得なくなったり、急な一時金徴収が必要になったりする可能性があります。
適切な資金計画を維持するためにも、長期修繕計画を約5年ごとに見直し、建物の現状や物価変動などを反映させ、修繕積立金の額との整合性を確認することが推奨されています。
計画と積立金のバランスが取れているかを確認し、必要に応じて積立金の額を見直すことで、将来的な資金不足のリスクを軽減することができるでしょう。
大規模修繕工事の内容(回数ごと)
大規模修繕工事の内容は、建物の築年数やこれまでの実施回数によって変わる傾向があります。
回数を重ねるごとに、工事の範囲が広がったり、補修だけでなく交換や機能向上を目的とした工事が増えたりするのが一般的です。
1回目の大規模修繕工事(築12~15年頃)
1回目の大規模修繕工事(築12~15年頃に実施されることが多い)では、建物の主要な部位に大きな問題が発生しているケースは比較的少なく、部分的な補修が中心となる傾向があります。
特に、外壁のひび割れ補修や塗装、シーリングの打ち替えなどが主な工事項目です。
屋上防水についても、部分的な補修や既存防水層を残した状態での改修が一般的です。
2回目の大規模修繕工事(築24年~30年頃)
築24年~30年頃に実施されることが多い2回目の大規模修繕工事では、建物全体で経年劣化が進み、工事範囲が広くなるとともに、交換や撤去・新設が必要な項目が増加します。
外壁だけでなく、バルコニーの手すりや隔板(パーテーション)・玄関ドア・サッシといった部位の劣化も進むため、これらの修繕や交換も検討されます。
屋上防水も、既存の防水層を撤去して新たに形成する工事が必要になる場合があります。
金物(集合ポストやベランダ隔板など)も錆や破損が進み、2回目工事での交換を検討することが推奨されます。
3回目以降の大規模修繕工事(築25年~30年以上)
築25年~30年以上経過した頃に実施される3回目以降の大規模修繕工事では、建物ほぼ全てを対象とした大規模な工事となることが多くなります。
給排水管や電気設備といったライフライン関連設備の交換、エレベーターの交換なども視野に入ってきます。
また築年数の経過により、現行の建築基準や消防法などの法改正への対応、建物の耐震性の向上・省エネルギー化といった機能・性能向上を目的とした改修工事が伴うケースも増えます。玄関ドア・サッシ・手すりなども、劣化が進行している場合は交換が必要となります。
また特定の工事項目には、以下の通りそれぞれ一般的な目安周期があります。
| 項目 | 修繕・交換の目安周期 | 備考 |
| 屋上防水 | - 部分補修・既存層を残す修繕:12~15年ごと- 撤去・新設:24~30年ごと | 防水仕様により異なる(アスファルト:15~25年、シート:10~15年、ウレタン:10~12年) |
| 金物 | 特に明記なし(2回目の大規模修繕時に交換検討) | 集合ポストやベランダ隔板など、経年劣化により交換対象となる |
| 消防用設備 | - 屋内消火栓・連結送水管:23~27年- 自動火災報知設備:18~22年 | 消防法に基づき定期点検義務あり |
| 機械式駐車場 | 18~22年ごとに装置入れ替え検討 | 2回目の大規模修繕で検討されやすい。都心部では解体・平置き化も増加。平置きはコスト低めだが維持必要 |
| 給水管・排水管 | - 給水管:2回目の大規模修繕時に検討- 排水管:3回目以降に検討 | いずれも老朽化により段階的な更新が求められる |
| エレベーター | 築26~30年を目安に交換検討 | 安全性・性能維持のため、耐用年数に応じて交換が必要 |
これらの目安はあくまで一般的であり、個別のマンションの実際の劣化状況や設備の種類、使用頻度などによって、適切な時期は異なります。
分譲マンションと異なる建物の周期
ここまで分譲マンションの大規模修繕について解説してきましたが、すべての建物が分譲マンションと同じ周期で大規模修繕を行っているわけではありません。
公共建築物や賃貸マンションなどの大規模修繕周期は、分譲マンションとは異なる傾向があります。
実際、分譲マンションと同じ鉄筋コンクリート造であっても、公共建築物や賃貸マンションでは12年程度の周期による大規模修繕工事は実施されていないのが実情です。
特に収益ビルの大規模修繕は、分譲マンションとは異なり、基本的にオーナーの判断により行われます。
分譲マンションのように、ガイドラインによって周期の具体的な年数が示されているわけではありません。
ただし、収益ビルであっても建築基準法に基づく定期報告制度は適用され、建物の規模によって1年ごとまたは3年ごとの定期報告が必要となり、外壁の全面調査も必要となる点は分譲マンションと変わりありません。
収益ビルにおいても建物の劣化は確実に進むため、適切な補修や修繕を行うことで資産価値を保っていくことが重要です。
さらに収益を確保し向上させるためには、単なる維持管理だけでなく、新しい技術を導入するリノベーションを行い、建物の付加価値を高めることも重要になります。
店舗やオフィス・賃貸住宅は、入居者がいなければ賃料収入が得られません。
建物の状態を適切に保ち、魅力的なリノベーションを行うことは、リーシング(入居者付け)を行ううえでも重要な要素となります。
また、建物の所有者には管理責任があり、例えば商業ビルで漏水事故などが発生した場合、テナントへの賠償責任が発生する可能性もあるため、安全性の確保はビルオーナーの義務であり、不具合には適切に対応する必要があります。
まとめ
マンションの大規模修繕工事において「12年周期」が広く一般的とされてきましたが、これは国土交通省のガイドラインにおける例示や、建物材料の劣化タイミング・特定建築物定期調査の義務化など、さまざまな要因が影響して定着したものであり、あくまで目安に過ぎません。
法律で厳密に定められたルールがあるわけではなく、建物の実際の状況に応じた判断が最も重要です。
マンションは一棟ごとに劣化状況が異なります。適切な時期を見極めるためには、築年数や経過年数だけで判断するのではなく、まず建物診断を実施して、建物の現状を正確に把握することから始めることを強く推奨します。
建物診断の結果と長期修繕計画を照らし合わせることで、マンションにとって最適な大規模修繕のタイミングを見つけることができます。
必要に応じて専門家の意見も参考にしながら、総合的に判断することが大切です。
建物の劣化を放置してしまうと、より深刻なダメージにつながり、結果的に修繕費用が増大してしまうリスクがあります。
長期的な視点で計画を立て、建物の劣化状態を見極め、修繕の時期を逃さないことが、将来的なコスト負担を抑制し、マンションの資産価値を適切に維持していくためには不可欠です。
適切な時期の工事は、目先の費用だけでなく、長期的な視点で見れば経済的なメリットにもつながる傾向があります。
マンションに安全で快適に長く住み続けるために、そして大切な資産価値を守るために、一度ご自身のマンションの長期修繕計画や建物の現状を確認してみてはいかがでしょうか。